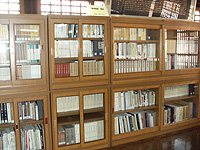津山洋学資料館
現在は新館(こちらのページです)へ移設されています。
| |洋学資料館(建物)|洋学資料館(展示物)| | ||||
| ※是非一度お出かけください。津山の洋学は見ごたえがあります。 | ||||
| ◆休館のおしらせ◆ 建設工事が進んでいる新館への移転作業のため、4月1日(水)から新館のオープン(22年3月の予定)まで、休館いたします。しばらくの間、展示見学・資料閲覧ができませんが、新しい資料館のオープンにどうかご期待下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
||||
|
津山洋学資料館の建物
▲軒先
▲倉庫
▲箕作阮甫さん。 津山駅に立っている銅像と同型だそうです。
※池田豊太郎(多くの名建築を残した棟梁)
※磯島政吉(幻の名工といわれる建具師) 明治37年に出雲で生まれたと伝えられていますが、その経歴は定かではありません。先祖は出雲大社の宮棟梁であったといい、「磯島のちり返し」といわれる独特の面取を考案するなど、稀有の名工として知られています。昭和17年岡山で亡くなりました。 ★利用案内 開館時間:午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) 休館日: 月曜日、祝祭日の翌日、12月27日〜1月4日 入館料: 大人¥150(団体¥120) 高校生・大学生¥100(団体¥80)※団体30名以上 交通: 市内循環ごんごバス「東松原」下車徒歩1分 中鉄バス「松原向」徒歩5分 中国自動車道「津山インター」から車で10分 津山洋学資料館 |
▲本館は神社仏閣風の外観で、屋根は千鳥破風入母屋造り。桧皮葺きの上を銅板で張りさらに玄昌石の天然ストレートで葺くという凝った造りです。
▲天井の壁面
▲天井
▲ケヤキの玉目の腰板や、カウンターの一枚板の巨木は今ではなかなか見ることの出来ないものです。
▲展示室に行きがけにある庭
▲事務所の外観
▲展示室へ続く
▲この扉の向こう側に展示室があります。
▲奥の部屋へと続く
▲窓も素敵です。 内部はモザイクパーケット貼で大正期の優れた建築技術を示すものとして、注目されています。 |
▲津田真道の銅像
▲宇田川玄真の銅像
▲宇田川榕菴の銅像
▲素晴らしい資料がぞくぞくあるそうです。
▲津山藩医久原洪哉使用の駕籠 この駕籠の製作年代は明らかではありませんが、漆の下張りに慶応3年の日付のある和紙が使われていたことから、幕末のころに新調されたものか、また修理されたものと思われます。
▲かごの中にはひじ当てや背もたれがありました。
▲思わず軒をみてしまいます。
▲庭は休憩所になっていました。
▲綺麗なレンガ
▲窓 |
||
| ※津山洋学資料館にご協力いただきました。 | ||||