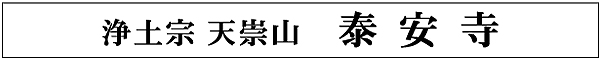泰安寺
|
浄土宗 天崇山 泰安寺(2009.9.18) 御霊屋はこちらから |
||||
|
泰安寺由緒沿革 |
||||
|
▲庫裏
▲入口のお地蔵様 本堂の内陣中央の須彌壇に御本尊として阿弥陀如来が祀られている。
▲おじぎそう
▲ガヤの木は碁盤を作ると最高の木だそうです。
▲赤白のさるすべり 泰安寺年中行事 1月/新年法要 3月/お彼岸 8月16日/盆施餓鬼会 9月/お彼岸 12月/年末法要 浄土宗 天崇山 泰安寺 美作西国三十三所観音霊場 津山市西寺町12 電話:0868-23-8141 |
▲本堂
▲境内
▲客殿玄関 松平家代々の追遠法会が行われ旧藩主が参拝されるにふさわしい葵の大きな鬼瓦、玄関の破風構えなど堂々たる建造物である玄関踏板は鶯張りである。
▲弁天堂 弁財天をお祀りしている。 もとインドの川の神で、その像は六臂(び)弁財天で古代色豊かなものである。 知恵・弁舌の徳をそなえるとされる女神、のちに吉祥天と混同され、財産や福を授ける神とされ、七福神のひとつとして信仰されている。
▲二木刀自頌徳之碑 二木幾代刀自は女子教育の先覚者的存在で、夙に裁縫並びに茶道(千家裏流)・華道(未生流)の奥義を究めた師であった。(後ろの桜の木は先代の住職が植えられたそうです。)
▲佛足跡石 お釈迦様が入滅前に残されたといわれる足裏の跡の形を石の上に刻んだものである。
▲鐘楼 第二次世界大戦中に、献納を余儀なくされたが、昭和51年新調寄進したもの。
▲べんがら地蔵(いぼとり地蔵) |
|
▲泰安寺の寺標 当山入口の右側に寺標、その左手に宇田川家三代墓所の案内石碑がある。
▲入口の溝
▲山門 4間・1間そして高さ3間半の切妻造りであるが、葵の紋入りの本瓦葺きで当時を偲ばせる堂々の建物である。 右手には飲酒者は境内に入ることを禁止する石碑がある。
▲不動尊堂 この堂は天保時代まで津山鶴山城西御殿城内にあり代々の藩主はこのご本尊を祈願佛として信仰厚く、その霊験まことにあらたかなものがあるとされていた。
▲不動尊堂
▲不動尊堂
▲境内
▲庫裏(住職や家族の居間) 葵の大きな鬼瓦など堂々たる建物で、山門を入るとすぐ右手にある。 |
|
|
宇田川家三代墓所 平成元年11月12日宇田川三代墓所が泰安寺に移転完了し、法要が行われる。宇田川家は日本の近代文化発展の創始者として郷土の大偉人である。 津山の「宇田川家三代顕彰実行委員会」が中心となり、東京の多摩霊園より泰安寺墓地に移転改葬され津山の史跡となる。
▲随分古い無縁仏
▲泰安寺にある、今井家のお墓です。 この今井家はここの土地を寄附してくださったり、津山の今井橋はこの今井家が出資なさったそうです。 |
▲宇田川家三代墓所
▲宇田川家の
▲宇田川榕菴妻の墓
▲宇田川興斎妻子 早世した後妻阿梶と、その子の撤四郎の墓 |
▲宇田川槐園(玄随)の墓
▲宇田川榛斎(玄真)
▲宇田川榕菴の墓 |
||
|
(2010年5月)津山市指定重要文化財の指定となりました。 泰安寺境内(史跡) (2012年2月20日)県重要文化財指定となりました。 県教委は県文化財保護審議会の答申に基づき、津山藩松平家文書(津山郷土博物館所蔵)を県重要文化財に、津山藩主松平家菩提所泰安寺(西寺町)を県史跡に指定すると発表した。 津山藩松平家文書など貴重な資料が残っている。 |
||||