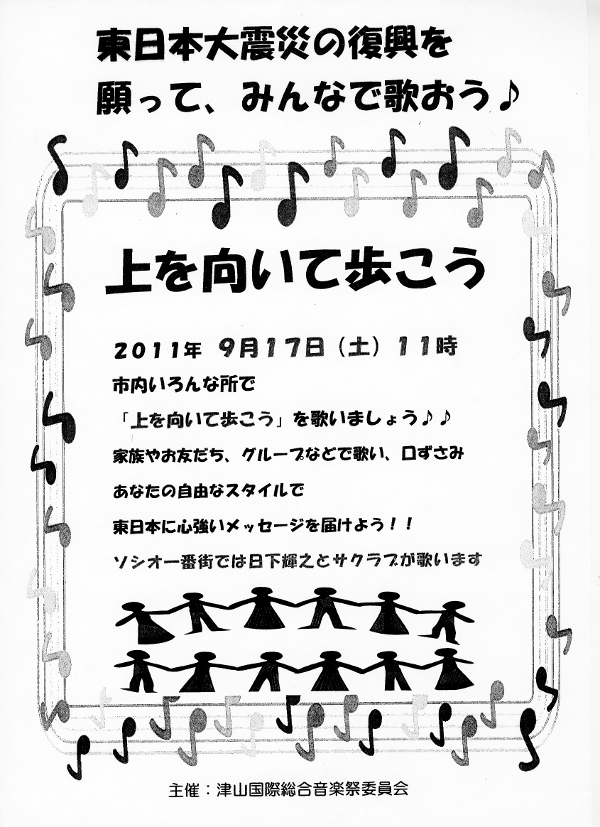因幡往来に隣接 山王権現を祀る日吉神社
日吉神社は聞き伝えによると、滋賀県の日吉大社から持って帰ったと言われています。大国主命の弟をお祀りしているとのことでした。太田町内会の宮総代の下山清さんは「昔は廻り舞台もあったが、終戦後に壊したのではないかと思います。そして、参道脇にはワラ家があって賑やかでした。また、日吉神社はすもうの神様なので境内には土俵があり、よく相撲をしていました。」とお話くださいました。日吉神社には記録も紛失して残っておらず、しかも荒れ放題だったのを下山さん達皆で立て直されたそうです。日吉神社は、川崎太田、玉琳、飯綱、東野介代、野介代東分の各町内会が氏子だそうです。毎年7月13日には「お湯立て」があるそうです。2011年10月16日取材