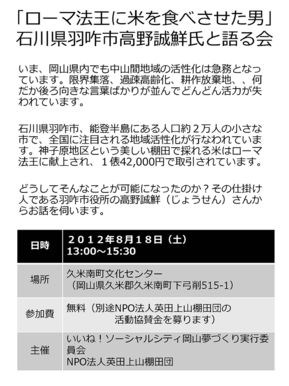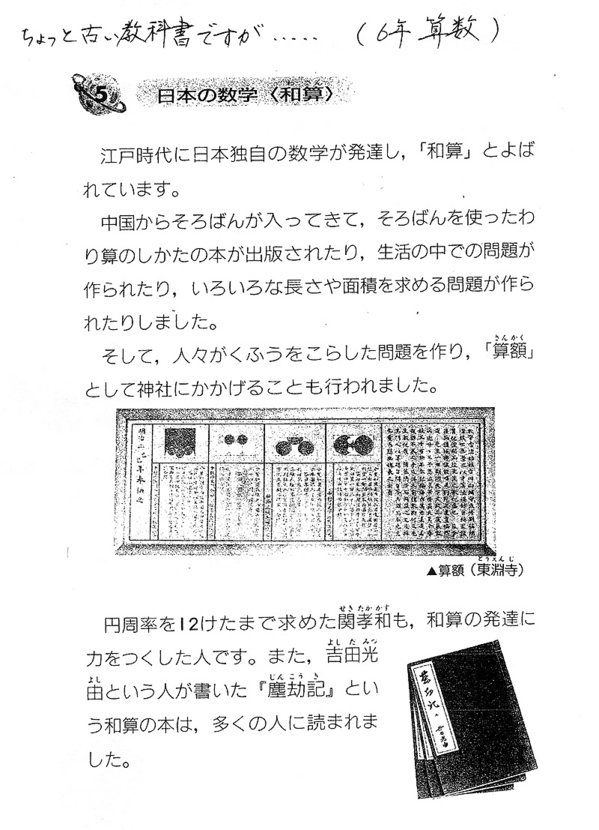津山市一宮の本光寺参道の前の小路を上がってゆくと美土路昌一氏の墓があり、横には碑が建っている。右上には「言論自由の語は之を守る為め死を辞せざる者のみ言い得る言葉なり」とあり、下方には「この夏は越せそうも無き米寿かな」とある。後者は死の三日前の絶筆である。


↑2015年12月7日現在は先祖代々の墓地で静かに眠っておられます。
(美土路昌一氏は明治19年7月16日中山神社の社家の一軒で生まれた。)




美土路家(現津山高校100周年記念館)の前の津高の門を入ってすぐ、よく伸びた二本の松がある。これは、はじめて空を飛んだライト兄弟の飛行場の松の種をもらって、母校の庭に寄付して植えたもの。
よく言っていた言葉「一歩退って人に接せよ」、「何ごとも、まず相手のことを考えよ」、「水流先を争わず」(文:津山市文化協会「津山の人物」より)
「現在窮乏、将来有望」これは津山市出身で市の名誉市民 美土(みど)路(ろ) 昌一(ますいち)氏が全日本空輸(ANA)の前身である「日本ヘリコプター輸送株式会社」創立時に掲げたスローガンです。
1886年(明治19年)、苫田郡一宮村(現:津山市一宮)で生まれた美土路 昌一氏は、旧制津山中学を卒業後、文学を志し早稲田大学文学に入学されました。苦学の中、文学の道を断念され大学を中退後、朝日新聞社に入社されました。
入社後は第一次世界大戦(青島戦)に従軍されたほか、上海、ニューヨーク特派員を経た後、編集局長として神風号による東京‐ロンドン間の記録飛行を成功に導くなどの活躍をされました。
その後、日本は戦火の渦に突入しますが、戦中、編集局長、常務取締役と朝日新聞社の要職にあった美土路氏は言論の弾圧にさらされます。