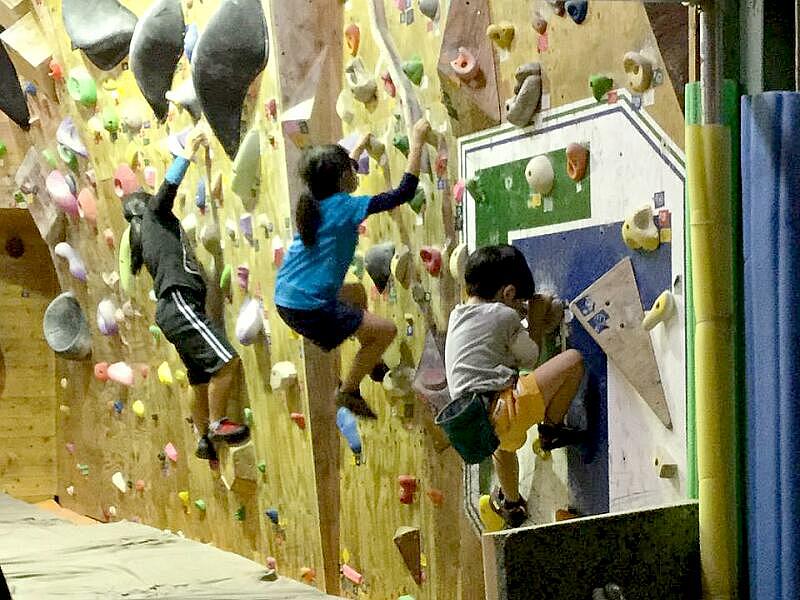備前国総社宮 岡山市指定文化財(史跡)
備前国総社 岡山市指定文化財(史跡)
古代律令制下、平安時代末ごろまでには、ほとんどの国に総社が設けられた。
総社とは、国司(国の長官)が逐一出向いて巡拝すべき各神社が、国内各所に分散して不便であるため、各祭神を国府の近接の一か所に合祀することで、参拝を略式化するために設けられたもので、国府直属の祭祀施設である。
備前国の総社は、備前国府(推定地)の北西丘陵に位置し、国司所祭の古社128の祭神を集めたものと伝えられる。成立の時期は定かではないが、およそ平安時代と推定される。律令制崩壊後は、氏神としての地域の信仰を集め、中世の神仏習合期、岡山藩による寛文の神社整理(1666~1667)を経て、現在に至っている。
現在の境内地付近には、惣社の内一、同二、馬場といった字名が残っており、かつては一町四方におよぶ広大な社地が広がっていたと考えられる。
昭和四十年七月に岡山市指定史跡に指定された。平成28年3月 岡山市教育委員会(文:案内より)
(2018年1月1日撮影)