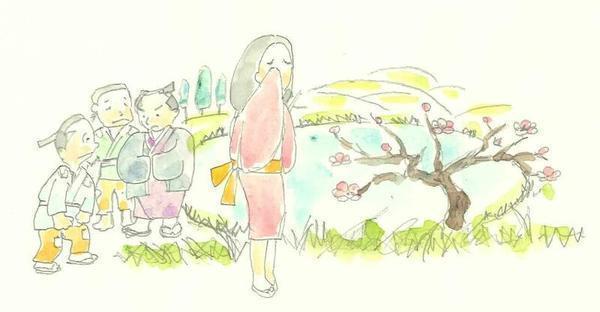法雲山 妙願寺書院北庭に建つ郷(渓花院殿)のお墓
忠政の後を継いで津山二代藩主になったのは関家の流れである外孫長継である。1年後の寛永12年江戸に着いたその日の2月11日、池田備中守長幸の息女お鶴(大御前)と婚姻した。その次年の寛永13年には、将軍徳川家光の命により江戸市谷御普請手伝いとあわただしい消光の中、紹向とのトラブルもあった。長継27歳の時である。
長継と紹向は従兄弟同士であって、長継は紹向を「親兄の如く」慕っていたのであるが、妙願寺再建立のことが紹向の意のままにならず、「諸子末寺一等に退院」したのであった。ここに注目すべきは「末寺」という表現である。四ケ寺が建立されて、本願寺がその寺号をいつ認めたかは定かでない。また、妙願寺が造営された後に寺中四ヶ寺誰が寺務をとっていたのかも不明であるが、寺院の形態として、妙願寺境内地南側に長泉寺・養元寺・教念寺・善正寺の四ヶ寺かあるいはその一部の寺が造営されていたことは間違いないと思われる。なお、長継の時代には盛んに寺社の造営が行われている。また、寺社とは別であるがこの頃は嗣子以外の男子に一家を創立させて分地を与え、幕府に願い大名の列に加えることが行われていた。