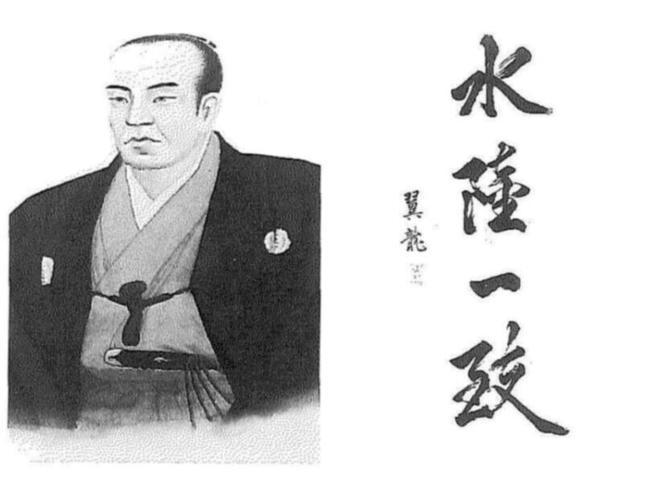イナママ「私は86歳で!え~んかっ!」
2023年7月8日、長雨が降り続いている日本列島、ここ津山市も例外ではなく雨が降っては止んでの繰り返しです。全国的に水害がとても心配ですね。被害にあわれた皆様お見舞い申し上げます。
さて、この日イナバ化粧品店に現れたのは3人の若者たち。みなさん口をそろえて「親がB'zの大ファンだったので自分たちもB'zのファンになってママに会いに来た。」そうです。ママ「私は86歳で、こんなおばぁ~ちゃんでえ~んかっ!」若者「ぜんぜん、パワ~がもらえてとても嬉しいです。」等など、ジョークを交えた楽しい会話が続いていました。