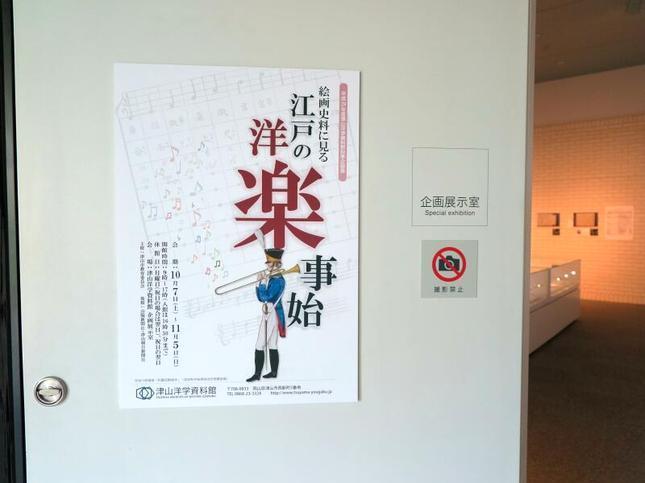柵原鉱山資料館(地下展示室)
エレベーターを降りると、そこはもう地下400mの坑道の中。
岩にダイナマイトを入れる孔をあけたり(削岩作業)、鉱石をすくったり(タイヤローダー)、かき集めたり(スクレイパー)、きみたちが見たことのない珍しい採堀作業が本物で見られるぞ。
柵原鉱山(やなはらこうざん)は、岡山県久米郡美咲町(旧柵原町)にあった、黄鉄鉱を中心とした硫化鉄鉱を主に産出した鉱山である。岩手県の松尾鉱山とともに日本を代表する硫化鉄鉱の鉱山であった。(文:美咲町HPより)(2018年1月21日撮影)