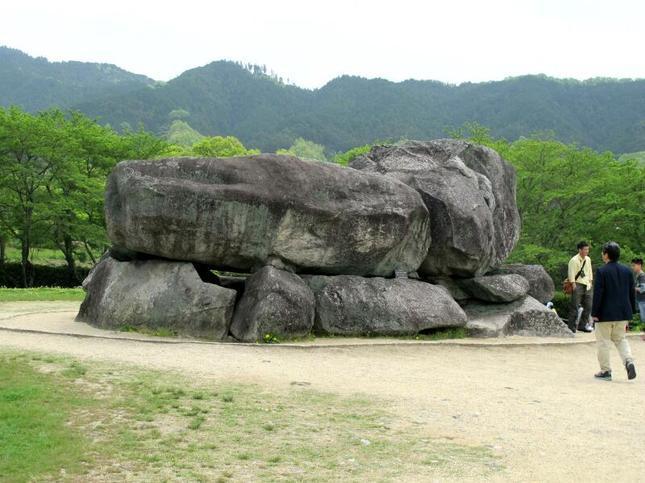東賀茂神社隣の安井大師堂
勝北町安井宇根にある大師堂は、通称庵と呼んでおり、真言宗の祖弘法大師の像を祀る堂宇で奥行二間半桁行一間半で大正元年に建て替えられ、そのご二度の修復をへて今日に至っている。
大師堂の建立の由緒は定かでないが、明治初期に毘沙門天が勧請されてから別名毘沙門さまと呼ぶようになった。
そこには、数本の石仏が並び、中でも中央の地蔵菩薩は美しい姿をとどめている。
天明、寛政年間、この地方に多くの石仏を遺した泉州の石工、松尾伊八らの手によって造られたのではなかろうか。天明年間は、天変地妖相次いで起き、国中の者は草の根、木の皮まで食い尽くし飢と病で多くの人が死んでいった過酷な時代であった。飢餓は、八年にも及び諸国の百姓は地獄の苦しみに喘ぎ、何に救いを求めようもない村の人達は、僅かな浄財を出し合い地蔵さんを建て死んでいった人々の供養と菩薩の慈悲にすがった。
安井庵文書を繙くと庵には、代々庵僧が寄寓していたことが伝えられており、天保時代より出羽の国の三九郎夫婦、生国因州の庵僧、旧浜田藩の松田佳次郎などの庵僧の墓が近くの草叢に眠っており、他国の人々を庵僧として温かく迎え入れた厚い人情を村の人々は今でも誇りに思っている。
大師堂のかたわらには大きな庫裡があって昭和二十五年に取り壊し今は、堂宇一つを残すのみとなった。
苫勝霊場二十五番札所の大師堂は、毎年桜の花の咲く頃、苫勝霊場めぐりの遍路で賑い村の風物詩でもあったが、今では知る人もだんだん少なくなり、毎月二十一日の大師の縁日に古老達によって念仏が上げられている。
(勝北町文化財保護委員平田安男記)(平成12年12月19日取材)