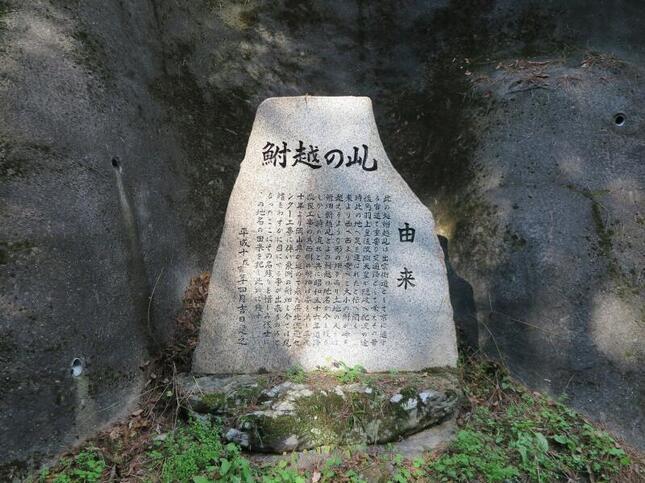「津山まち博」自分で焼いて美味しくいただく初雪
津山まちじゅう体験博2025~津山でしかできない特別な体験プログラム~
2025年10月27日、津山名産「初雪」とおかきを火鉢を囲んで焼き比べ、お抹茶もたててみよう!の言葉につられ、子どものころ「初雪や家で作ったかきもち」を焼いて食べていたのですが、焦げたり、しわかったりとうまく焼けなくて悲しかった思い出もあり、久しぶりにおいしく焼けた餅菓子を味わいたいと参加してきました。
案内文には「津山の伝統的な餅菓子「初雪」は焼くとサクッとした歯触りで口の中でスゥーと消えてゆき、まさに初雪が消えてゆくかのような食感が魅力。生地のままで食べられるのも特徴のひとつ。炭火の香りとともに、お好みの焼き加減やおかきとの食べ比べができる他にない機会です。」との説明もまた魅力的でした。