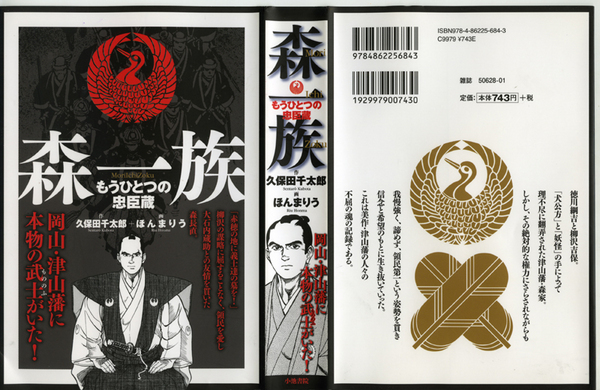岩間山 本山寺(美咲町)法然上人ゆかりの地
天台宗 岩間山本山寺(いわまさんほんざんじ)
大宝元年(701)頼観上人の創建で、本尊は観世音菩薩である。当初は南方の山頂に在ったが、天永元年(1110)現在地に移り、大いに発展して百廿十坊と言われた。
古来、山岳仏教の道場として、又、庶民信仰の霊地として栄えた。長承元年(1132)稲岡ノ庄(誕生寺)の漆間時国公夫妻が参詣、祈願して生まれたのが、後の浄土宗の宗祖と仰がれる法然上人(源空)である。降って江戸時代になると、津山藩の祈願所として、尊ばれ、又、森候の時代には、美作の天台宗の触れ頭であった。山内寺院のうち、遍照院・仏性院・梅元院の三院が院内頭であったが、今では皆、合併して本坊一ヶ寺となった。現在の境内地は四千二百坪、十余棟の堂塔伽藍は、昔に変らぬ面影を伝えている。
国指定文化財、本堂(1350)、三重塔(1652)、宝筐印塔(1335)
県指定文化財、常行堂(1519)、御霊屋(1652)、仁王門(1686)、長屋(1845)、宝筐印塔(1399)、鬼面(1362)、六角型舎利塔(1344)、絹本著色両界曼荼羅図二幅(鎌倉末期)
美咲町教育委員会 (案内板より)