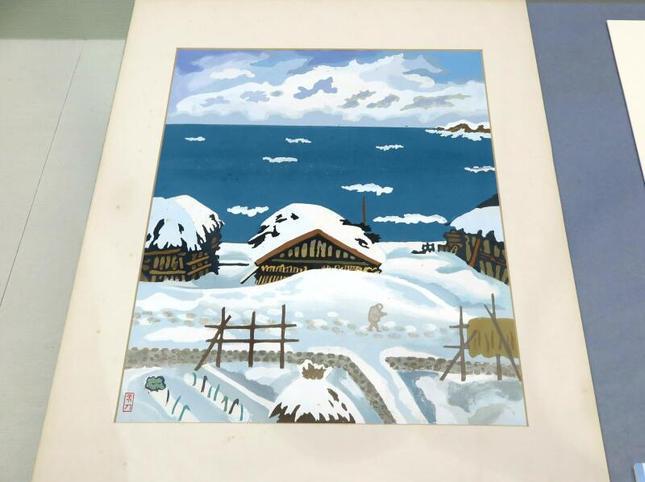平櫛田中美術館(井原市)・平櫛田中彫刻美術館(小平市)
平櫛田中(ひらくし でんちゅう)昭和54年12月30日逝去(107歳)
岡山県民が誇る井原市にある田中美術館を初めて訪れたのは十数年前で、今とは違う雰囲気の美術館でしたが、その時「幼児狗張子」(ようじいぬはりこ)に出会って衝撃を受けたのを覚えています。それはなんとも言い難い、田中さんの幼くして亡くなった長男をモデルにした彫刻でした。田中さんの作品を通して、だれもが田中さんの生き方、考え方そのものに感動するのだと思います。
また、田中さんが約20年間かけて制作した大作「鏡獅子」を、東京の国立劇場に飾るとき、国が2億円で買い上げようとしましたが、「お金はいりません。この作品は私一人で作ったものではなく、六代目菊五郎さんと2人でこさえたもんです。お金をとったら、あの世で六代目さんに会ったとき、あいさつのしようがないですよ。」と答えたそうです。(平櫛田中美術館HP)(平櫛田中彫刻美術館HP)