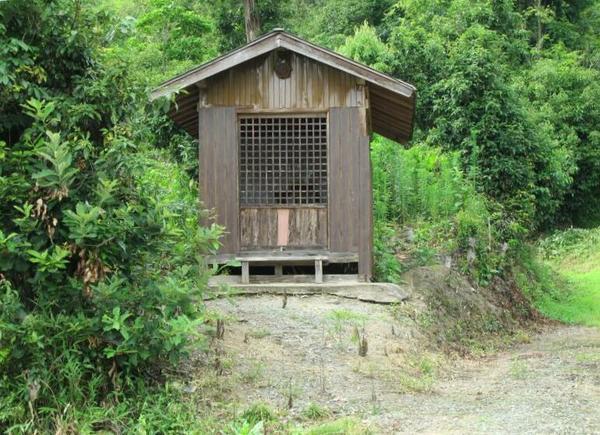【津山人】箕作秋坪(1825-1886)のエピソード
箕作秋坪は1825(文政8)年に菊池士郎と多美の二男として備中国下呰部村(あざえむら)に生まれました。13歳で父を亡くしますが、17歳頃から父の旧友・稲垣研嶽(いながきけんがく)の下で漢学を学び、さらに江戸へ出て箕作阮甫(みつくりげんぽ)に弟子入りしました。
1849(嘉永2)年には、大坂の緒方洪庵(おがたこうあん)の適塾に入門。この時にはもう箕作家の養子になることが内々に決まっていたようです。翌年、藩に正式に養子として認められ、さらにその翌年、江戸へ戻って阮甫の三女つねと結婚。新進の医師として活動を始めました。この時秋坪は27歳でした。
翌1852(嘉永5)年には、藩主松平斉民(まつだいらなりたみ)のお目見えもいただきました。