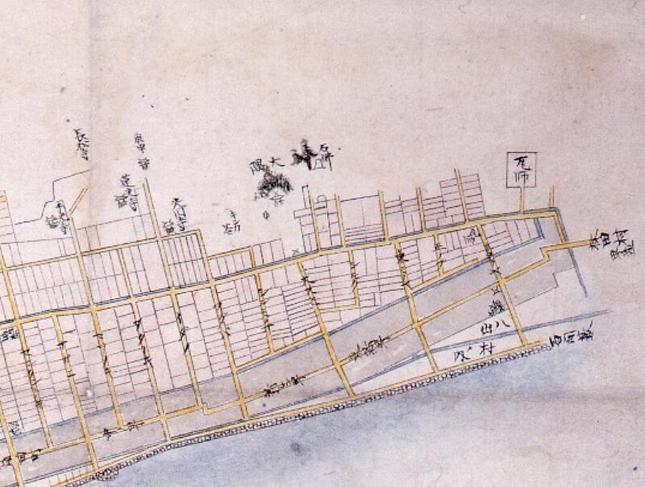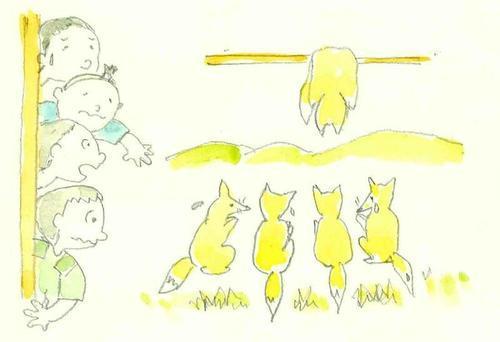白石不舎 文学碑(山下)
「佐保姫に合ふ靴をおく花の下」 白石不舎(しらいしふしゃ)
白石不舎(大正13年9月1日~平成24年2月26日)は西東三鬼に師事。以降、俳句教室や俳句結社「綱」を主宰。句集「作州」を発表。
三鬼の句墓碑や生誕地句碑を建立したほか、「三鬼顕彰全国俳句大会」「西東三鬼賞」「曲水の宴俳句会」の開催にも精力的に取り組み、直弟子として師の顕彰に努めた。
津山市出身。本名 白石 哲。津山文化センター 平成24年9月 設置
(文:『津山市文化協会創立60周年記念誌 津山文化』より)