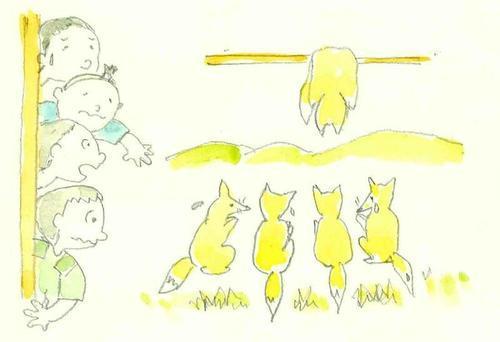名主の話『山西の民話』
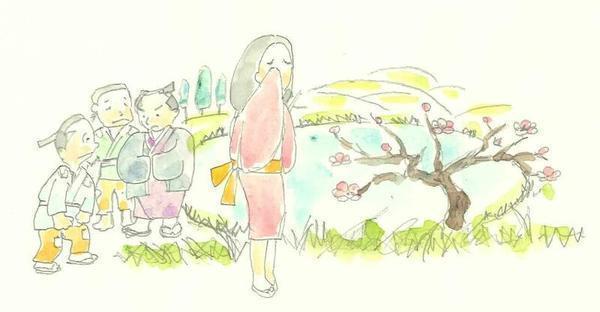 山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。
山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。
私の小さい時、冬の日に母が水車へ行って米を搗いて来たのをおぼえている。夏場は川の水は朝から翌朝まで、たんぼのかんがい用水として水車をまわすわけには行かなかった。夏の日、冬ためづきした「寒搗き米」でご飯をにてたべていると「スイ」くて変な味がしたが仕方なく文句も言わずに食べたものだった。また、たんぼも天水がだいじで、あぜを特に強くして、槌でたたいてむくろ穴をふせぎ、その上に泥を塗り、藁で日おおいをして更にもう一度泥をぬり水を一滴でも流さないように工夫をこらしたものであった。この天水田を「しる田」といって、夏も冬も水があった。