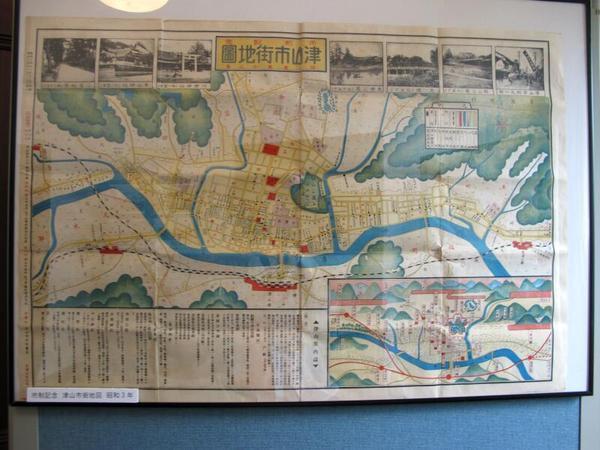【津山人】 多胡昭彦さん(日本のアマチュア天文家)
多胡昭彦さん(1932年生まれ)は日本のアマチュア天文家で、10数個の彗星や新星の発見者です。小惑星 (7830) Akihikotagoに命名されました。また、1996年に設立された岡山県柵原町の町立のさつき天文台で天文学の普及に尽くされました。
発見した彗星は、C/1968 H1 多胡・本田・山本彗星、C/1969 T1 多胡・佐藤・小坂彗星、C/1987 B1 西川・高見沢・多胡彗星がある。新星としてはV1493 Aql (みずがめ座新星1999)、V2275 Cyg (はくちょう座新星2001、no. 2)、V574 Pup (とも座新星2004)、V2467 Cyg (はくちょう座新星2007)があります。