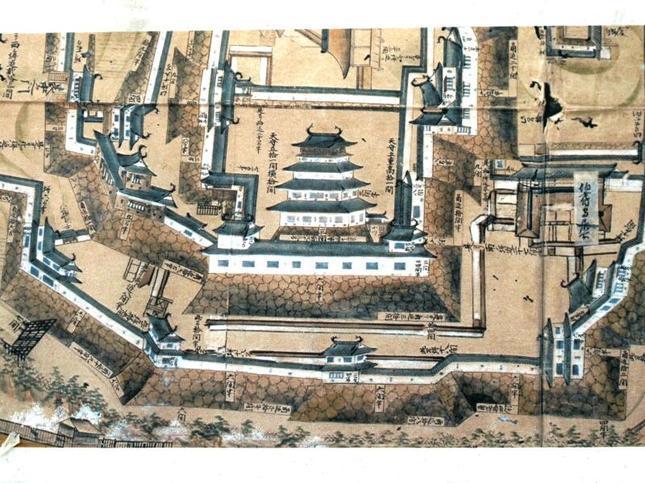諏訪神社(勝田郡勝央町河原)
当社の創建年月は不詳であるが、河原鏡山に古吉野庄の総社として創建されたと伝われている。
天平5年(733)9月20日庄内の住民が集合して大祈祷を行って以来、この日を大祭日定めたとされ、当日は縫い物、畑仕事を禁じられた。
長久3年(1042)古吉野庄の氏子の総意により、信州諏訪大社の御分霊(建御名方命)を勧請し、合祀した。
安元2年(1176)広戸風の大烈風で本社が大破したので、移転地を信州諏訪に似たところとして、風害の少ない現在地に再建した。(御祭神 建御名方命 速秋津姫神 素盞嗚命 譽田別命 大國主命
倭建命 大己貴命)
神社の境内にある神木(びゃくしん・いぶき)は本社移転時に諏訪豊前守藤原安盛宮司が手植えされたと伝えられ、樹齢800年の神秘な樹姿を見せる。また、十郎、徳丸(村人)の蛮勇で河原田圃開発の祈祷に使った伝承を持つ「雨乞い石」がある。(文:岡山県神社庁HPより)