2018 第47回つやま市民スポーツ祭
2018年10月7日(日)津山陸上競技場に於いて、第47回つやま市民スポーツ祭が執り行われました。少し、曇り空ではありましたが、"スポーツをみんなで楽しもう"を合言葉に今年も大勢の人が元気いっぱいリレーやテニス、ゴルフ、ターゲットバードゴルフ、すもうなどなど競技を楽しんでおられました。また、陸上競技場前南側広場では、健康コーナーや模擬店、フリーマーケットコーナーが出店して賑やかです。
2018年10月7日(日)津山陸上競技場に於いて、第47回つやま市民スポーツ祭が執り行われました。少し、曇り空ではありましたが、"スポーツをみんなで楽しもう"を合言葉に今年も大勢の人が元気いっぱいリレーやテニス、ゴルフ、ターゲットバードゴルフ、すもうなどなど競技を楽しんでおられました。また、陸上競技場前南側広場では、健康コーナーや模擬店、フリーマーケットコーナーが出店して賑やかです。
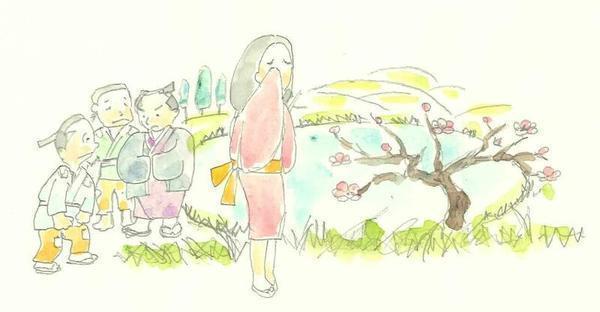 山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。
山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。
私の小さい時、冬の日に母が水車へ行って米を搗いて来たのをおぼえている。夏場は川の水は朝から翌朝まで、たんぼのかんがい用水として水車をまわすわけには行かなかった。夏の日、冬ためづきした「寒搗き米」でご飯をにてたべていると「スイ」くて変な味がしたが仕方なく文句も言わずに食べたものだった。また、たんぼも天水がだいじで、あぜを特に強くして、槌でたたいてむくろ穴をふせぎ、その上に泥を塗り、藁で日おおいをして更にもう一度泥をぬり水を一滴でも流さないように工夫をこらしたものであった。この天水田を「しる田」といって、夏も冬も水があった。
まちの文化財 信仰絶えない"いぼ神" 勝北町 因幡街道に昔の祠残る
勝北町日本原の家並みがある西はずれ、通称「日本坂」と呼ばれているところに国道五十三号線と旧国道にはさまれ、谷のようになった中をその昔、津山と鳥取を結んだ因幡街道が通っていた。
そのころは、この街道を行き来した旅人が多かったであろうが、今は国道改良工事により、通行はできなくなっている。街道の面影は失われ、わずかに踏み跡だけが残っている道にかたわらに「水神様」「すりばち様」または「いぼ神様」と呼称される祠(ほこら)がある。
石造りの祠の中に、小さなお杜が祀られ、杜前には岩の間からかすかに流れる泉をたたえた、直径約十七㌢ほどの"すりばち状"の水たまりがあり、そのそばには柄杓が置かれている。
昭和の初め、私どもが子供のころです。イボができたとき、村人はこの泉の水をイボに塗り、早く治ることをお祈りしました。その後いつの間にかイボがなくなったと聞き、幼心に不思議に思ったものでした。
平成30年度津山洋学資料館春季企画展 「明治150年記念 洋学資料館所蔵資料から見た文明開化と美作の医学」より
維新前夜
幕末の日本は、ペリー来航、開国から、尊皇攘夷の高まり、長州征伐、尊王倒幕、大政奉還と続き、戊辰戦争へとつながる動乱の時代でした。事件・出来事に対する情報が錯綜し、流言飛語が飛び交うなど騒然とした雰囲気が社会を包んでいました。そのような中で、人々はより正確な情報を求めました。友人知人からの手紙では、自身の近況のみならず、巷に流れる噂や、知り得た情報が報告されるようになります。また、幕末には「新聞」が生まれましたが、中には発行者にとって有利な状況を作るべく、それぞれの立場から見た情報を庶民に提供するものもありました。
このような混乱の中で、江戸幕府から新政府へと政権は移り、270年続いた江戸時代は終わりを告げたのです。しかし、民衆にとっては、それで混乱が沈静化したわけではなく、その後に続く新たな変化の始まりでもありました。
知恵を願う文殊菩薩 筆などを供え素朴さ残す
勝北町山形の字寺尾、八幡神社の上り道のかたわらに、石造りの「文殊菩薩」と彫った文字塔が、ひっそりと立っている。
石塔の高さ七〇cm、表面の下方に蓮華を彫り、その上の中央に「文殊菩薩」右方に「文政七年」「世話人忠蔵」左方に「申八月日」「其外連中」と刻銘されている。文政七年といえば、今から一六七年前、世話人忠蔵を中心として、文殊信仰に篤いこの付近の人びとによって、建立されたものであろう。
まちの文化財 日本野・開祖の墓地
顕彰される福田五兵衛
日本原の街のはずれ、日本坂の上の丘に苔むした自然石の墓碑がひっそりと建っている。この墓碑には
元文五申年 雲仙信士霊 九月初六日
此聖霊者国々嶋々無残
順廻仕依而諸人稱日本
五兵衛是以此所日本野ト申傅也
日本野元祖 俗名 福田五兵衛 と刻まれている。
作陽誌によれば「正徳(1700年)の頃、日本廻国をして、終りにこの地に供養塔を築き、その側らに小さき家を建てて、往来の人を憩はしめ、あるいは行臥したる者などを宿めてもっぱら慈愛を施せしかば、誰言ふとなく「日本廻国茶屋」と呼びならわせしを、後には略して日本とばかり唱うるごとくなれり。後にその野をも日本野と稱するも時勢と言うべし」と記されている。
この墓の王は、雲仙信士で、日本野元祖福田五兵衛である。墓碑は、後世この地の人々が五兵衛の徳を顕彰して建てたものと思われる。死没した当時、広戸五穀寺の過去帳には「日本」の地名はなく、五兵衛の没後五十年を経て天明五年六月八日「日本忠助の子」とあり、それ以後死亡者には、ことごとく「日本」という名称が付けられいる。
「日本原」の地名は、日本廻国をして善行を積んだ福田五兵衛を偲んで名づけたものと思われる。
(勝北町文化財保護委員長・金田一記)(『平成5年発行:勝北風の里探訪』より)
近長陣屋領内であった勝加茂西中の真言宗新善光寺境内鐘楼の巽位に近長代官沼尻又治郎の墓があり、自然石の碑に
沼尻又次郎重遠墓
先考仕吾 土浦候嘉永癸丑四月為近長令赴任癸丑七月罹病以五日沒于府舎無子故以甥重道為嗣葬新善光寺謚曰 沼蓮院甫仭義照居士
と刻まれて居る。碑文には病死と記されてあるも事実は近長大庄屋甲田猪右ヱ門方に於いて自刃したものであり、其死因に就ても俚傳があるも明確でなく、此没後甲田猪右ヱ門が公用の道中、攝津尼ヶ﨑附近に於て沼尻氏の為めに討たれたとのことが傳へられてゐる。
岡山県津山市中村の新善光寺の参道に道標一基がある。これは八十八ヶ所の道しるべで、「天保13年、八十三番一ノ宮道、右一番霊山寺道」と書かれている。(参考:『勝北町の文化財と石造美術』より)
近世において廻国聖と称す一種の聖が日本六十六国の霊場を遍歴し、一部づつの如法経を納めて歩いた。
到るところで費用を勧進してゆき、頭を布で包み白衣に笈を背負い鉦を叩いて善根を勧進して歩く。一種特別な服装で遊行するものもあれば、巡礼姿に身をやつし廻国する農民も多かった。
しかし本物の廻国聖でさえ六十六国を廻り尽くしたものはすくなく、遠国の道のりを他国の風物に接し、疲れと病を気づかう不安との戦いののち無事本願成就の暁に地元に廻国の記念碑を建てた。
廻国記念地蔵菩薩/中村 新善光寺/供養塔 一体
虚空蔵山 求聞持の寺(高野山真言宗 美作八十八ヶ所霊場 第74番)
萬福寺に如意宝珠をお奉りする融通堂があったとのいい伝えがありました。由来は萬福寺と同じです。
平安時代後期の経塚と如意宝珠を護持するために、實仁和尚が昭和五年融通堂を再建され、昭和五十八年四月二十一日に本四国八十八ヶ所霊場を勧請すると共に、求聞持の寺として新寺建立されました。