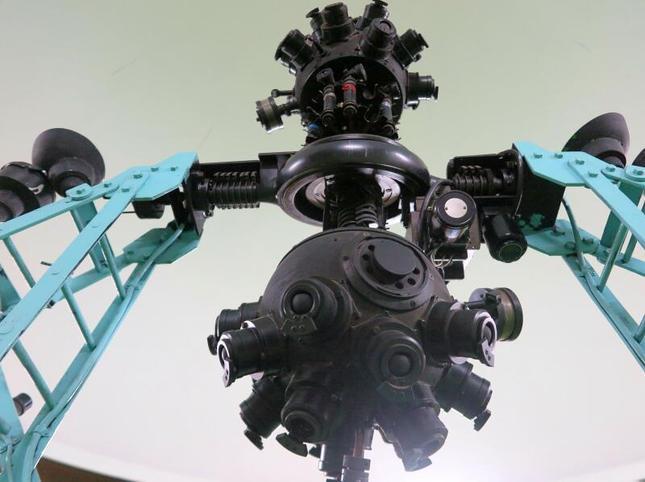つやま自然のふしぎ館「世界のクワガタ・カブトムシ・カナブン・ハナムグリetc」
2022年8月4日、連日34度を超すような暑さが続いていますが、世界中の昆虫たちは、おそらく灼熱の太陽の下で頑張って生きていることでしょう。さて、8月と言えば子ども達は夏休みに入り、「つやま自然のふしぎ館」では、親子連れの皆さんが何組も来られて館内は賑やかです。
今回は昆虫たちを取材してきました。クワガタ・カブトムシと言えば、黒・茶色しか見たことがない私には、クワガタ・カブトムシ・カナブン・ハナムグリetcなど、見れば見るほど、どこがどう違うのか判りませんが、美しい模様の世界中の昆虫たちが沢山いますので是非お楽しみください。