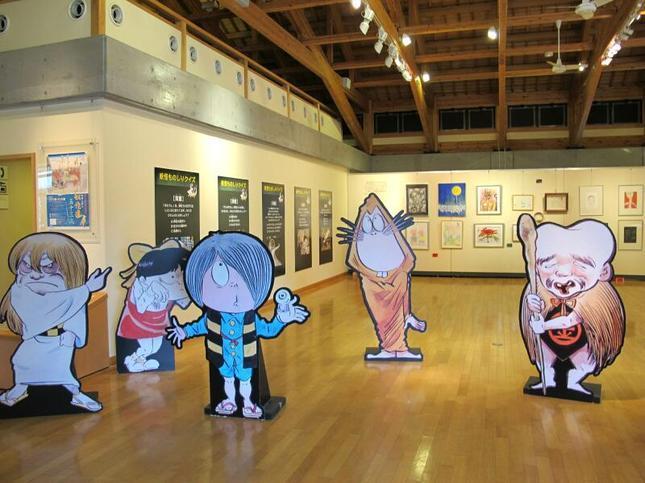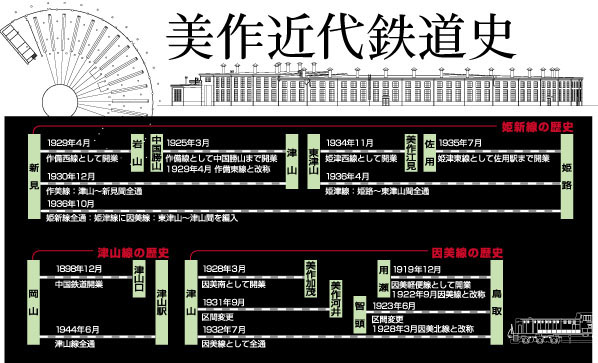少林寺拳法グループ総裁 宗由貴氏の講演
2016年8月20日(土)津山鶴山ホテルに於いて、「少林寺拳法のこれからの歩むべき道」と題して、少林寺拳法グループ総裁の宗由貴氏の講演がありメモしてきました。
少林寺拳法は、開祖が戦後荒廃した日本や、日本人が自信を無くしていたのを見た時、自分に何か出来ることがないか? 自分の手でもう一度人のために働く人を育てたい。社会を良くしていくには、自分のことと同じように他人のことも大切にできる人間をひとりでも多く育てる ‐人づくり‐ しか方法はないと考え、その手段として教え・技法・教育システムを兼ね備えた少林寺拳法を創始しました。
今や世界37か国まで大きくなりました。少林寺拳法に流派はなく、世界中どこへ行っても、同じ教え、同じ技、同じ教育システムです。
開祖は様々なものは作ってきたが、その時代その時代で必要なものと必要でないものがあるように思います。指導者は今の時代に何が必要かちゃんと解って指導しなければならない。中学・高校生の若い年代が志を持ち、何とかしようと思ってくれるようにならなければならない。