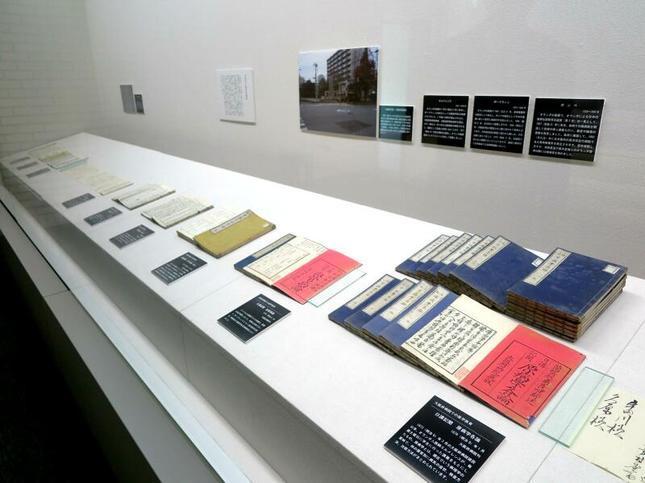極楽寺略縁起
美作国小桁山極楽寺は天台宗延暦寺の末寺であります。
当山は文徳天皇御宇天安二年(西暦858)、極楽寺の開祖天台宗第二の高祖慈覚大師円仁が西國行脚の砌、当山の民家に止宿せしめたまう。
覆う事三日三夜、しかる間に雲中に阿弥陀如来光明赫として左右の大士こと光を放ち、此の山の絶頂の影に向いたまいて大師遙拝して不思議かな云々。
本堂阿弥陀堂は山頂にあり堂跡(堂屋敷)なおあり、山の頂を安養の峯と稱し、北の谷を成仏谷、南の谷は不老谷、山を於桁と云う寺を極楽寺とす。
本堂の周囲には、観音堂・虚空蔵堂・大子堂・鐘楼・寺坊・十二院、一町東に二王大門あり。
過ぎし七百年以来の災難で坊舎を失い埋没して、残る所の四ヶ寺は、藤元坊・久保之坊・西之坊・極楽寺であり云々。
中略
備前岡山の城主宇喜多直家は、花房助兵衛職秀(もとひで)をして荒神山に城を築かせ職秀城主となる。職秀は日蓮宗の強信者であるため極楽寺の僧豪顕に日蓮宗えの改宗を強く迫ったが、豪顕は可とせず拒否しました。
職秀怒りて僧豪顕を追放し寺を取壊その用材を持ち帰えりて人馬の住家にと工事は進みましたが、完成を目前にして無風の時にも拘らず倒壊し人馬の多くが損傷する所となる。その後荒神山城は廃城となる豪顕帰えりて一字を営む。
後法孫円慶帰えりて荒廃した堂を修復す。本堂、千手観世音菩薩をもって本尊となす。脇侍不動附釈迦地蔵、毘沙門、荒神の像を安す。
「美作圀久米南條郡小桁山極楽寺 本尊千手観世音略縁記 住法明院」による。