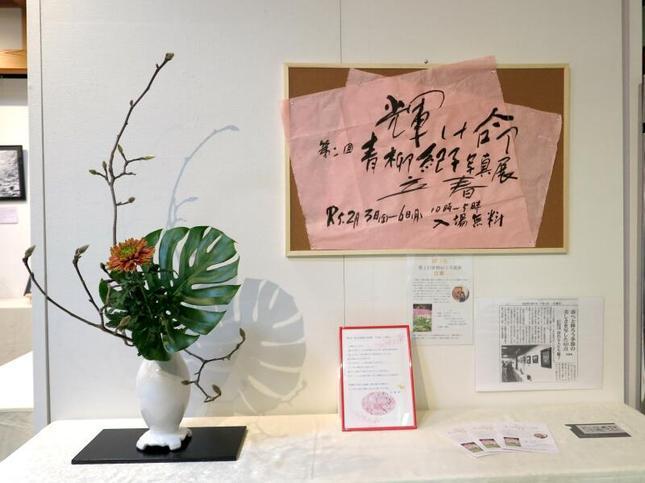2023 尾所(おそ)のさくら満開!
2023年4月9日満開の尾所のさくら (2022年のさくらの様子)(「尾所の桜」枝の折損の様子)
今年の冬の豪雪で折れた、岡山県指定天然記念物「尾所の桜」ですが、折れた姿を見た時には随分心傷みましたが、春になり元気いっぱい花を咲かせてくれていてほっとしました。
この尾所のさくらですが、西暦1450年 年号宝徳2年の頃、山伏が倉見越えの途中ここで休み、持っていた杖を残したまま出立ちした その杖が根づいて今の桜の木になったものと伝えられているこの桜の木は、当村大田進氏より阿波村へ寄贈されたものだそうです。