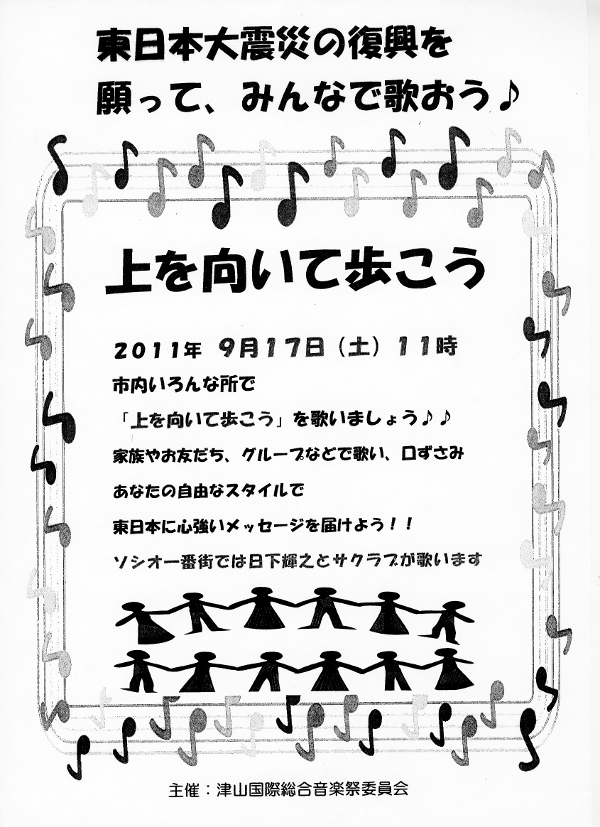津山徳守神社秋祭りに出動しただんじり16基
★津山だんじりの歴史/総鎮守徳守神社の祭礼は、初代藩主森忠政が慶長9年(1604)に社殿を増宮した際に氏子達が練り物を出したことに始まる。【現在、県の重要有形民俗文化財に指定されている津山だんじりは28臺(徳守神社20臺、大隅神社7臺、総社宮1臺)】
★津山だんじりの個性/松平宣富をはじめ、松平歴代藩主やその家族も度々津山城の一角の「赤座屋敷」から祭りを見物した。第5代藩主康哉は宮川門を開け町民を城内に引き入れ、第8代藩主斉民は城内で祭りに加わる。天保13年(1842)、祭りに出動するだんじり数に制限が設けられ、徳守神社が6基、大隈神社が2基との藩命が下された。この時の制限が、隔年、3年ごとなどの出動間隔として残っている。現在は各町内会が出動の有無や間隔を自由に決めているが、結果的に各町内が経済的にも無理をせず、だんじりの伝統が長く受け継いできていることに大きな役割を果たしている。
★子供を大切にする津山だんじり/簾珠臺(宮脇町)をはじめ全てのだんじりに、宵、本祭りとも子供が乗る。これは地域の将来を担う子供たちを大切にする津山の200年ほど前から続く伝統である。(津山市HPより抜粋pdf)