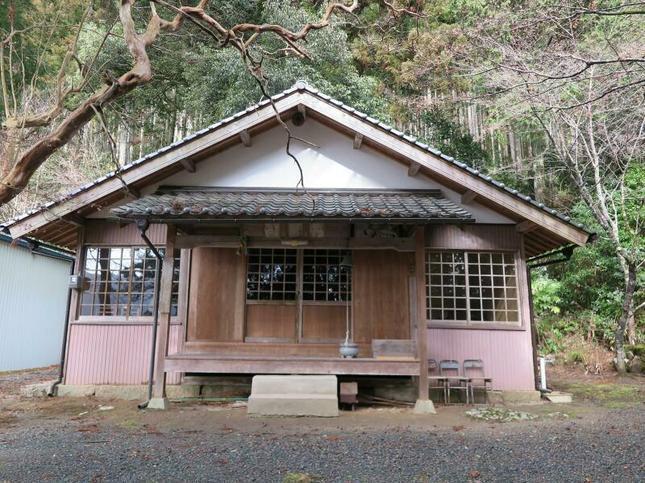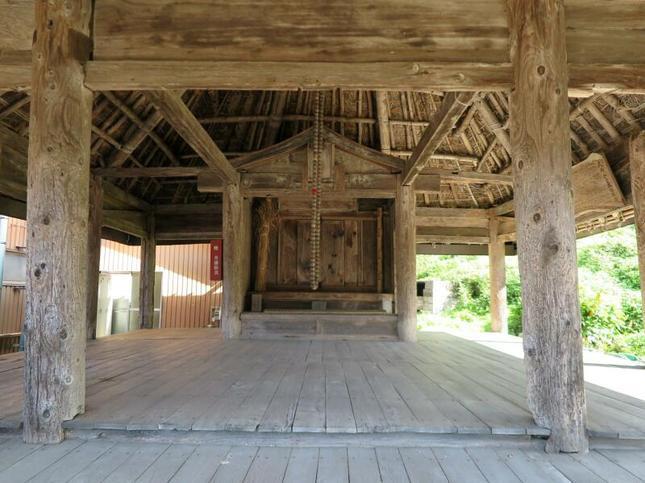津山圏域クリーンセンター多目的広場
2020年3月20日のお彼岸で春分の日です。新型コロナウイルスで世界中が恐怖に震え、学校も休校、親も休日となり、家族がストレスを発散させに来られているのでしょうね。親子で遊ぶ方がいたり、子ども達はそれぞれ遊具で遊んだり、サッカーをしたり、自転車に乗るなどして遊んでいました。また、大人は足湯で読書などしながらのんびりと過ごされていました。なお、足湯とレストハウス内休憩室は、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、2020年3月24日から一時閉鎖なっています。(2019年4月28日取材時のもの)