津山市加茂B&G海洋センターのプール
2019年7月28日津山市加茂町中原にある津山市加茂B&G海洋センターは体育館と屋内プールの複合施設です。今年の夏も暑い日が続いているので、子ども達もとても楽しそうです。
館内のプールは6コースあり、25mプールと幼児用プールがあります。(温水の設備がないのでプールは6月1日から9月30日までとなっています。)
2019年7月28日津山市加茂町中原にある津山市加茂B&G海洋センターは体育館と屋内プールの複合施設です。今年の夏も暑い日が続いているので、子ども達もとても楽しそうです。
館内のプールは6コースあり、25mプールと幼児用プールがあります。(温水の設備がないのでプールは6月1日から9月30日までとなっています。)
道祖神はいろいろな信仰を含んでいる。旅の神・道の神など考える人も多い。また村の入り口や峠などに祀られている所もあり、境を守る神、悪魔を追い払う神などともいえる。
道祖神は普通サエノカミ・サイノカミなどと呼ばれている。その信仰はほとんど全国にわたっている。道祖神の像塔が見られるようになるのは概ね寛文以後のことのようであり、それ以前はおそらく自然石を神体としていたと思われる。
山形の道祖神は磧石または花崗岩を丸くした自然石に「道祖神」と浅刻されており、色・形状は男性の象徴を思わせ、道祖本来の原形を偲ばせて微笑ましい。
勝北町が文化財に指定し長く保存している天然記念物部門の中に同町大吉の真言宗・五穀寺の紅梅(平成二年五月二十八日指定)があります。
この紅梅は、寺の山門を入った左側にあり、根元の周囲は二・六m、地上一mのところで二つの枝に分かれ、南の枝が一・三m、北の枝が一・六m、高さは五mあり、樹齢は三百年(元禄時代、一六九〇年ごろ)と推定される老樹。
寺の伝えによれば、今からおよそ二百二十年前の享保年間に、五穀寺は火災にあったといわれ、紅梅の樹齢からみて、この大火を凌いだ記念の木ともいえる。
2019年3月14日~17日までアルネ津山文化展示ホールに於いて、「 第39回 津山市医師会美術展」が開催されました。深雪アートフラワー、美し自然界の写真をはじめ、油絵、書、工芸、ブリザーブドフラワー、アートフラワー、造形、カリグラフィー等々の作品が展示されていました。
「春に山より下りてきて田の神になる山の神は五穀豊穣をもたらす農耕の神であり秋終りにはまた山に帰って山の神となる。」とも言われ山村に住む人たちの信仰する山の神の呼び名があり、ダンナサマ・ジュウニサマ・サガミサマ・ノタガミなどとも呼ばれている。
石造としては祠の物が多くあるが、自然石に「山神」「大山祗命」などと彫ったものが各地にもある。
西上の山形仙のふもとに天狗供養塔の石碑がある。この天狗供養塔は昔鞍馬山に住んでいた天狗(修験者)が、この西上の地に舞い降り無病息災を祈願し暮らしていた。
時が過ぎて天狗の話も薄らいでいたが、ある時土地の住民が家を建てて暮らしていると、主人が病にかかり祈祷師に拝んでもらうと「この家の下に鞍馬から来た天狗が居り、自然石で供養塔を立てなさい」とのお告げがあったと言われさっそく供養塔を建てると主人も良くなった。
天狗の命日には(旧暦一月十八日)主人が拝んでいたそうだ。また、供養塔の下には般若心経の一字一石の文字を書いた石を埋めてあるとも言われている。
大山みちは、信仰と牛馬の道です。霊峰伯耆大山への参詣を目指す旅人と博労座で開催される市へ向かう牛馬の群れが行き交った道です。大山みちは、岡山市の足守より粟井温泉~掛畑~千升乢~加茂市場~尾原~真庭市鰻田~鹿田~落合~久世~三坂峠~禾津~藤森~延助~内海乢を経て、鳥取県御机~鍵掛峠~大山寺に通ずるルートです。現在ではその殆んどが一般道路に併合吸収され、往時の姿を留めている箇所はあまり見ることは出来ません。
現在、「大山みち」を6分割して、歩く会が実施されていますが、今回はその5回目(5区)に当たります。5区のコースは2コースに分かれます。本道は、柞乢越えで距離も短く急ぎの旅人に利用されて来ました。もう1つのコースは、湯原温泉に1泊して休養を取り、旧二川村の三世七原、小童谷(湯原ダムにより水没)を経由して、野田で本道に合流する道でしたが、現在は消滅してたどることは出来ません。
歩く会は、あと6区を残すのみとなりました。第1回は平成26年に既に終えていますが、釘貫小川から三坂峠を越えて久世に至る峠道です。この間は全体の約70%が山道です。第5・6区も山中の道で、それに次ぐ昔の面影を最も残している区間と言えます。 (第2回の様子はこちら)
自由と民主主義のために闘った人々の、精神的ささえともなった、戦前の革命的民主的出版物をひとりでも多くの人達に見てもらおうと、毎年「戦前の出版物展」を開催しております。
この冊子は、同時開催で開かれた講演会「片山潜の青春・故郷における片山潜の労働と学習」河原要(片山潜記念館事務局長)氏の講演を要約したものです。なお河原氏の講演内容は、片山潜の生家や記念館を訪ねるときの参考になるものと思われます。『嵐の中の青春』林直道著と共にお読みいただければ幸いです。(文:2015年7月15日片山潜記念館だより創刊号より一部を転載)
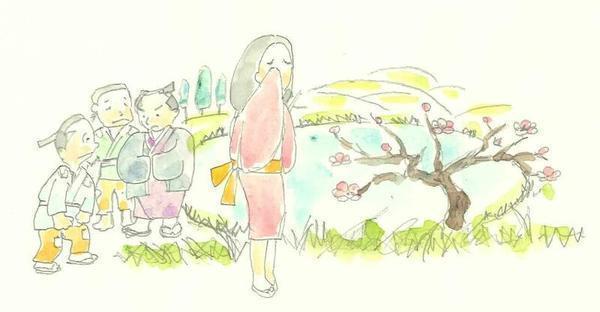 山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。
山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。
私の小さい時、冬の日に母が水車へ行って米を搗いて来たのをおぼえている。夏場は川の水は朝から翌朝まで、たんぼのかんがい用水として水車をまわすわけには行かなかった。夏の日、冬ためづきした「寒搗き米」でご飯をにてたべていると「スイ」くて変な味がしたが仕方なく文句も言わずに食べたものだった。また、たんぼも天水がだいじで、あぜを特に強くして、槌でたたいてむくろ穴をふせぎ、その上に泥を塗り、藁で日おおいをして更にもう一度泥をぬり水を一滴でも流さないように工夫をこらしたものであった。この天水田を「しる田」といって、夏も冬も水があった。
まちの文化財 日本野・開祖の墓地
顕彰される福田五兵衛
日本原の街のはずれ、日本坂の上の丘に苔むした自然石の墓碑がひっそりと建っている。この墓碑には
元文五申年 雲仙信士霊 九月初六日
此聖霊者国々嶋々無残
順廻仕依而諸人稱日本
五兵衛是以此所日本野ト申傅也
日本野元祖 俗名 福田五兵衛 と刻まれている。
作陽誌によれば「正徳(1700年)の頃、日本廻国をして、終りにこの地に供養塔を築き、その側らに小さき家を建てて、往来の人を憩はしめ、あるいは行臥したる者などを宿めてもっぱら慈愛を施せしかば、誰言ふとなく「日本廻国茶屋」と呼びならわせしを、後には略して日本とばかり唱うるごとくなれり。後にその野をも日本野と稱するも時勢と言うべし」と記されている。
この墓の王は、雲仙信士で、日本野元祖福田五兵衛である。墓碑は、後世この地の人々が五兵衛の徳を顕彰して建てたものと思われる。死没した当時、広戸五穀寺の過去帳には「日本」の地名はなく、五兵衛の没後五十年を経て天明五年六月八日「日本忠助の子」とあり、それ以後死亡者には、ことごとく「日本」という名称が付けられいる。
「日本原」の地名は、日本廻国をして善行を積んだ福田五兵衛を偲んで名づけたものと思われる。
(勝北町文化財保護委員長・金田一記)(『平成5年発行:勝北風の里探訪』より)