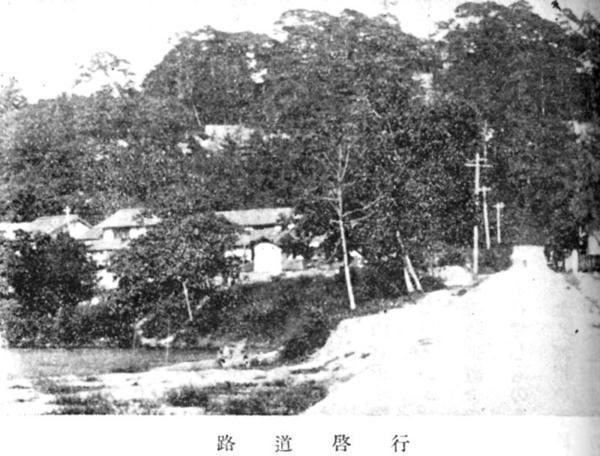ロバート キャンベルさんを招き「曲水の宴」を再現。
曲水の宴《動画1》《竹内津山観光協会長挨拶》《キャンベルさんのお話》《動画2》
流觴曲水ともいう。「觴」とは盃のこと。陰暦の3月上巳の日や3月3日に開催され、緩やかに蛇行しながら流れる水の岸辺に座して、流れ来る盃が自分の前に到達するまでに詩歌を詠ずるという風流な行事で、古代中国にその発祥があるという。水辺で行われていた禊ぎに関連する行事から、遊興の催事へと変化したといわれる。
中国の事例では「衆楽雅藻」の序文でも「永和之蘭亭」と称されている如く、永和9年(353)3月3日に開催された曲水宴が、後に王羲之の書作品「蘭亭序」により広く知られることになった。
日本にも古くから伝わっていたらしく『日本書紀』や『万葉集』にも曲水の宴を行ったことが記載されている。
明治3年(1870)に衆楽園で行われた曲水の宴では、詩を成した者は盃を取り、できなければ飲めないという定めであったが、流水には盃だけではなく、こなもちや酒の肴も流されており、鴎の群れが波に揺れる様であり、また落ち葉が流れ下っていく様であったと描写されている。(文:公益社団法人津山市観光協会チラシより抜粋)