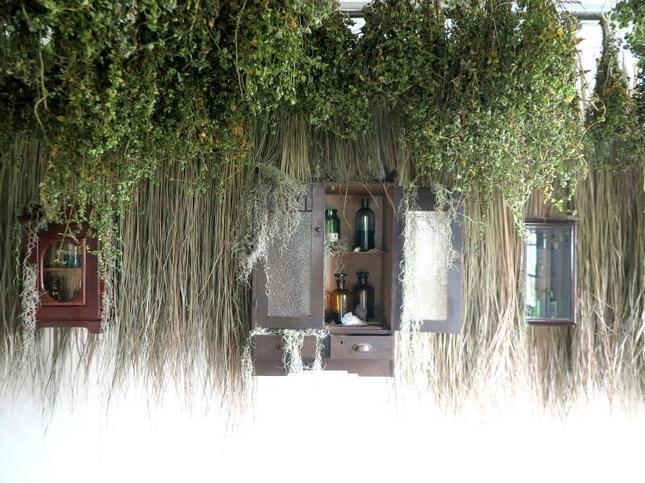観光庁の特別体験事業「津山城晩餐会」を開催!
晴れの国・岡山 森の芸術祭、また、11月16日(土)からの津山もみじまつりに合わせ、公益社団法人津山市観光協会DMOは16、17日、観光庁の「特別体験事業」として採択された補助事業として、津山の歴史や文化を知る講演や花火鑑賞、日本舞踊パフォーマンスなどを楽しむツアー「津山城晩餐会」を開催。両日とも参加者の約半数がドイツ、オーストラリア、ブラジル、フランス、オランダなどの訪日外国人が占めた。
日本文化研究者のアレックス・カー氏による歴史講話では、戦国武将の概要や津山城の歴史、初代藩主森忠政の津山城築城、森家と松平家の歴史、宇喜多家の紹介などを実施。森蘭丸の悲劇を、創作日本舞踊「佳卓」による演舞と琵琶楽曲で表現した演目などが参加者の関心を引いていた。また、宇喜多家に扮した武将隊も勝鬨を参加者とあげるなど会場は大いに盛り上がった。
晩餐会では、地元津山の素材をいかしたイタリアン料理が振る舞われた。中でも、地元「つやま和牛」を使用した炭火焼ローストが好評を博した。
宇喜多家に扮した武将隊も勝鬨を参加者とあげるなど会場は大いに盛り上がった。