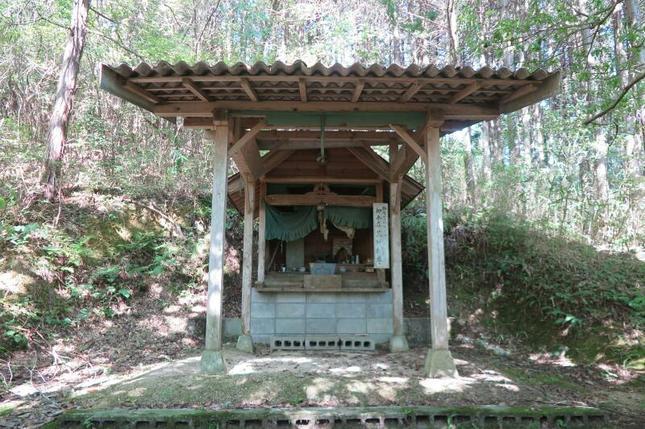高野本郷の国道53号線沿いに立っている石碑
高野本郷に立つ石碑ですが、通るたびに気になっていたので高野公民館の館長にお聞きしたら、「調べてはみたのですが、地区の方にお聞きしても解らなかった。」のだそうです。
知人に聞いたら「享保5年を調べると、美作地方は作物が不作で8月に入ると、雨が多く田は青できとなり、見入りが心配されている矢先、9月13日(西暦 1720年 10月14日 )には大霜が降り、干害と霜害とにより大凶作となったため10月百姓の多くが津山に嘆願に出かけている。
享保6年(1721)前年の干害、早冷えで、農作物は収獲皆無の状態になった。これらの凶作と関係があった石碑とも考えられますし、嘆願書を提出すると代表が責任を取らされ処刑されたことかもしれませんね。」とのことでした。(2018年10月24日撮影)