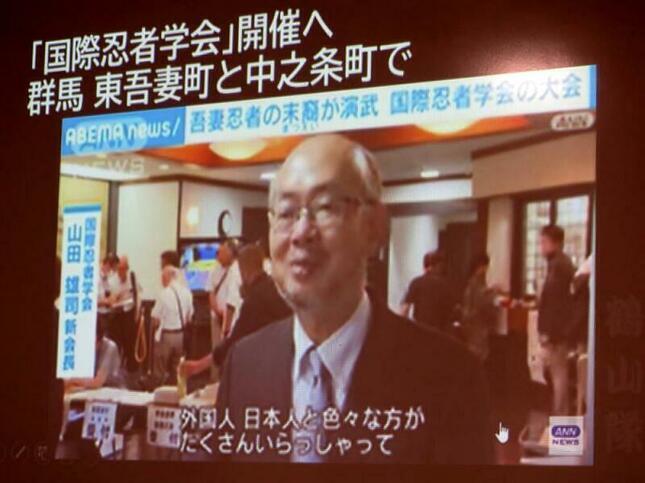プレミアムインバウンドツアーで津山を体験!
2025年10月24日(金)~10月26日(日)に、台湾、ポーランド、アメリカ、オランダ、ドイツ、スペインなどの13名が津山のサムライ文化や伝統的文化を堪能できるプレミアムなツアーに参加。
津山の「ハレ(非日常) とケ (日常)」をテーマとしたリアルでオーセンティックな体験をこの日限りで開催。初代美作国津山藩主・津山城主「森忠政公」の菩提寺「本源寺」にて東洋文化研究者「アレックス・カー」氏によるサムライ文化講話と森家当主との対談、津山まつり徳守大祭でのだんじり曳き体験、祭り前日の宵まつり体験、日本舞踊家「白鳥佑佳」氏の日本舞踊、本源寺でいただく精進料理、津山市の日本酒造見学を贅沢に詰め込んだ津山市ならではの内容となりました。(写真・文:公益社団法人 津山市観光協会提供)