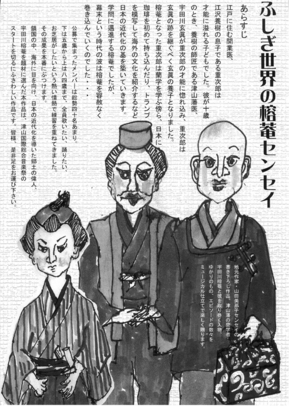構の城(2011.4.16貞考母子の碑より望む)
津山市院庄字構にあり、一町四方が城域となっている。はじめ院庄城といったが築城の年代は明らかではない。
正平15年(1360)、山名時氏とその子師義は兵4千5百騎を率いて赤松貞範の属城を攻めようとして、その将小池中書、福依八右衛門を篠向城(真庭郡久世町大庭)に、淀井丹波守、武田刑部左衛門を高田城(真庭郡勝山町)に向わせ、自分は精兵をもって院庄城を囲んだ。城兵は僅かに六百余りであったので、城将江見八郎兵衛景信および住井吉行、渡辺刑部少輔等は敗死して城は落ちた。村の東南に墓趾があり、この地を吉行といっている。正平17年6月(1362)、山名時氏はまた兵5千を率いて院庄に入り、近国の諸将を招いて備前備中の諸国に向かった。
その後康正2年(1455)、城将山名掃部頭の上洛の虚に乗じて赤松氏の将中村五郎左衛門が来攻した。掃部頭の子は戦に敗れ城を棄てて伯耆に逃れた。次いで山名氏が大挙来襲し互いに勝敗があって、戦の止むことがなかったという。
元亀2年(1571)、宇喜多氏の将花房職秀が来攻して杉山為国と戦ったが為国は戦死し、職秀の将難波信明もまた戦没した。その墓趾は院庄の西方西町にある。
これより後院庄城を改めて構城とし宇喜多氏は片山秀胤にこれを与えた。天正11年(1583)6月、毛利の兵が構城を攻略したので宇喜多の将花房職之兵を率いて構城を囲み奪い返した。秀家は芦田馬之丞およびその子作内に命じてこれを守らせた。
宇喜多氏が亡んで、慶長8年森氏が入封するに及んで構城を修築しようとして1年余り院庄に留まったが事情があって中止し、今の津山に築城した。寛永15年(1638)、その城跡を壊して大部分を農地とした。
注 天正年間、作備線(現在の国鉄姫新線)の敷設工事のため土砂が掘り採られて、今は本丸跡の一部を残して農地となった。現在その一角に貞考母子の碑が建っている。(昭和54年10月23日発行:院庄誌より)