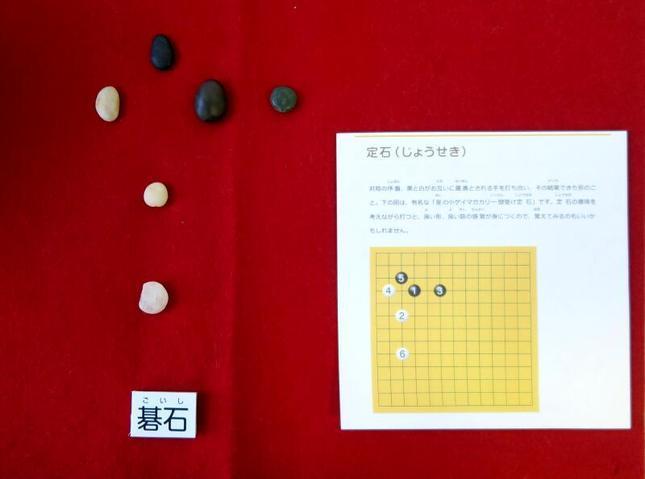「再発見☆考古資料展」12月4日まで
2020年9月7日久しぶりに「津山弥生の里文化財センター」へお伺いしてきました。私の苦手な古代社会の人々の生活を女性の視点で教えていただき、何だか少し古代の人々への関心が増してきました。
☆器台から埴輪へ
弥生時代の日常の土器である壺・器台が、墳丘墓に置かれる特殊器台・特殊壺を経て、古墳に立てられる埴輪へと変化する過程を模式図で表しました。
弥生土器の壺・器台と特殊器台・特殊壺との違いは、赤く塗られていること、特殊な文様で飾られていること、そして土器のサイズであることがわかります。
それでは、特殊器台と円筒は埴輪の違いはどこにあるのでしょうか。器台と埴輪の足元に注目すると、器台の足元は大きく外側に張り出していますが、埴輪の足元には張り出しがなく、まっすぐになっています。
この違いは、設置する方法が違うために生じています。器台は地面の上に据え置くので、倒れないように足元をおおきく外側に張り出させます。一方、埴輪は地面の中に埋めて立てるので、埋めやすいように筒状のままにしています。
特殊器台から円筒埴輪へ変化する過渡期に作られた特殊器台形埴輪は、特殊な文様で飾られ、特殊器台の特徴をよく残していますが、足元をみると、張り出さずに筒状のままとなっており、地面に埋めて使われていたことがわかります。





 http://www.e-tsuyama.com/
http://www.e-tsuyama.com/