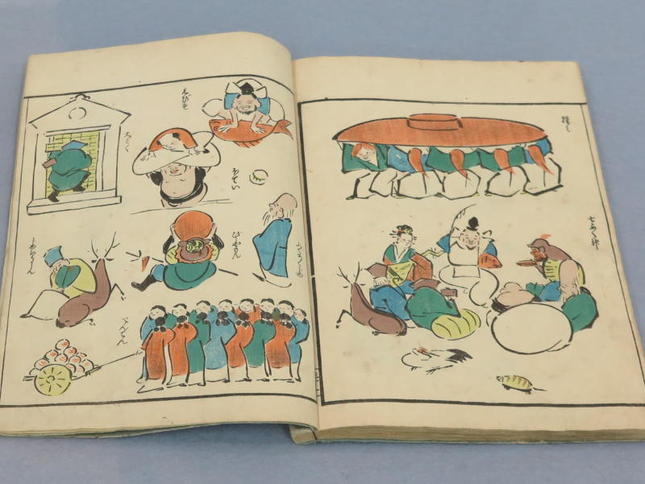長法寺多宝塔で、ご開扉・檀中先祖供養・戦没者慰霊法要
2023年6月18日(日)(午前10時~正午)津山市井口 にある長法寺多宝塔にて、多宝塔ご開扉・檀中先祖供養・戦没者慰霊法要がありました。
天台宗長法寺の多宝塔は、創建1150年を記念して造られたもので、平成5年着工し、平成8年3月完成する。津山市内唯一の多宝塔となっています。大津市の石山寺にある国宝の多宝塔をモデルにしたつくりで、高さ約25メートル。二重の塔はヒバ材を使用、屋根には銅板を施し、頂上には金色の相輪を取り付けている。塔内には大日如来の座像を安置している。
本尊:大日如来
約1300年前、インドで誕生した「密教」で、最上位にいる仏様で、日本では最澄(さいちょう)や空海(くうかい)によって広がりました。大日は「大いなる日輪」、すなわち「太陽」です。全ての仏様の起源は大日如来であり、大日如来は宇宙そのものであり、阿弥陀如来も薬師如来も全ての仏様は、大日如来が姿をかえた仏様です。