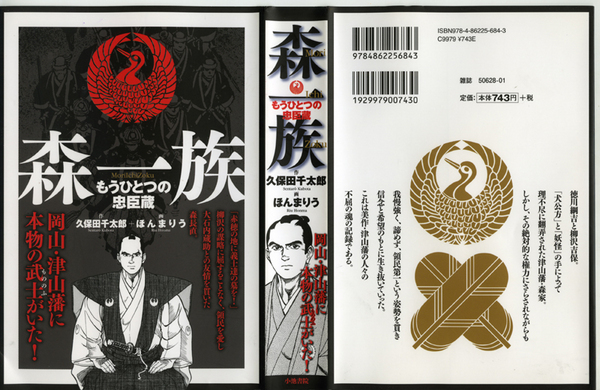加茂神社には崇道天皇の御陵がある。

加茂神社由緒
鎮座地 津山市加茂町公郷字菊水山1,399番地
御祭神 味鋤高日子根命/伊弉諾命/大山咋命/伊弉册命
配祀 大巳貴命/崇道天皇
祭日 大祭 例祭 10月第2日曜日/祈年祭 4月29日/夏越祭 7月25日に近い土曜日/新穀感謝祭 11月25日に近い日曜日
本殿 流造
末社 八幡神社、御先神社、美保神社、英霊神社、養老神社、若宮神社、天満神社
本社は、旧杉大明神と称し勧請年月興廃の沿革等不詳なりといえども、古昔より古老の口碑によれば往古苫北郡と称する時一ノ宮と尊崇される。桓武天皇の弟早良親王の御陵あるを以て崇道天皇と改称する。
明治6年2月加茂神社と改称し、尚、能野神社、元公郷上分字高場に、又、日吉神社公郷下分字日野目に古昔より鎮座ありしを明治42年5月2日本神社に合祀した。昭和7年7月7日雷火の為炎上し同8年4月再建立する。昭和43年3月26日、加茂町指定文化財に指定された第一号秋草双雀鏡は青銅の鏡(平安時代)で境内裏山から明治15年に発掘されたものです。加茂町観光協会協賛 (看板より)2012年8月22日取材