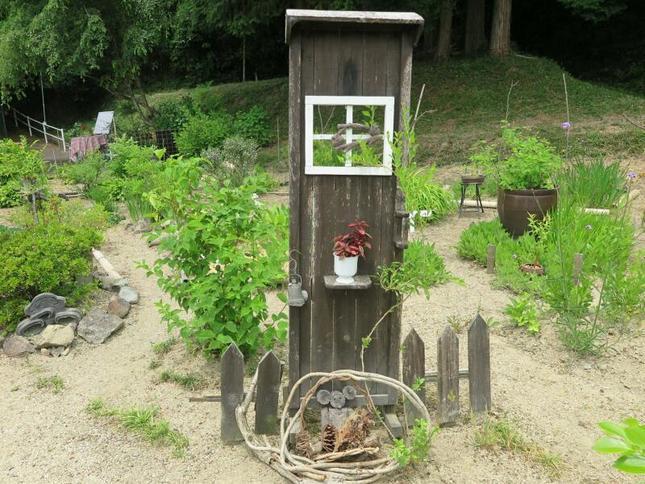備中国分寺(総社市)を訪ねました。
備中国分寺跡は、聖武天皇が天平13年(741)に仏教の力を借りて天災や飢饉(ききん)から人々そして国を守ること (鎮護国家)を目的に建てられた官寺の一つです。
その当時の境内は、東西160m、南北178mと推定されますが、江戸時代に再興された現在の備中国分寺があるため、 南門・中門以外の建物の位置は明らかではありません。しかし、創建当時の礎石が多く残されており、 当時を偲ぶことができます。国指定史跡。 (文:総社市公式観光WEBサイトより)(2019年5月3日撮影)