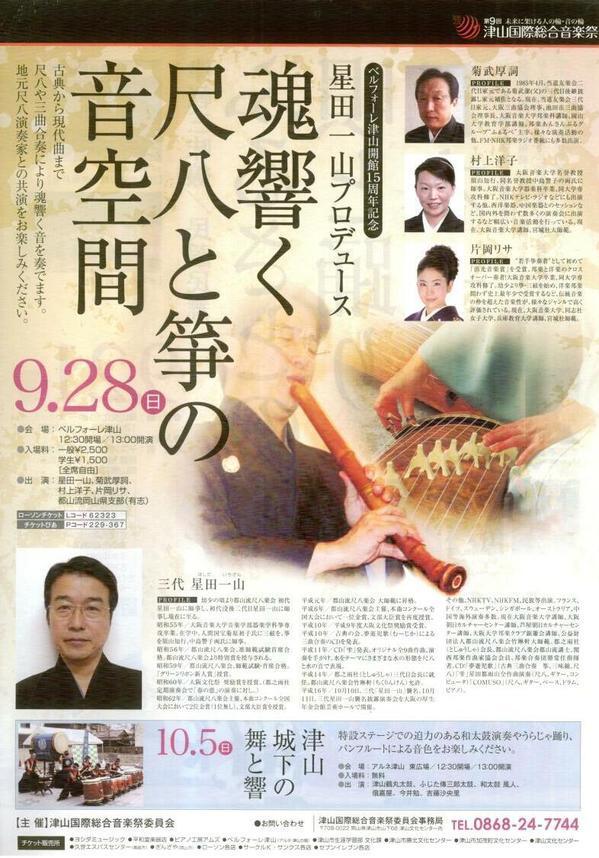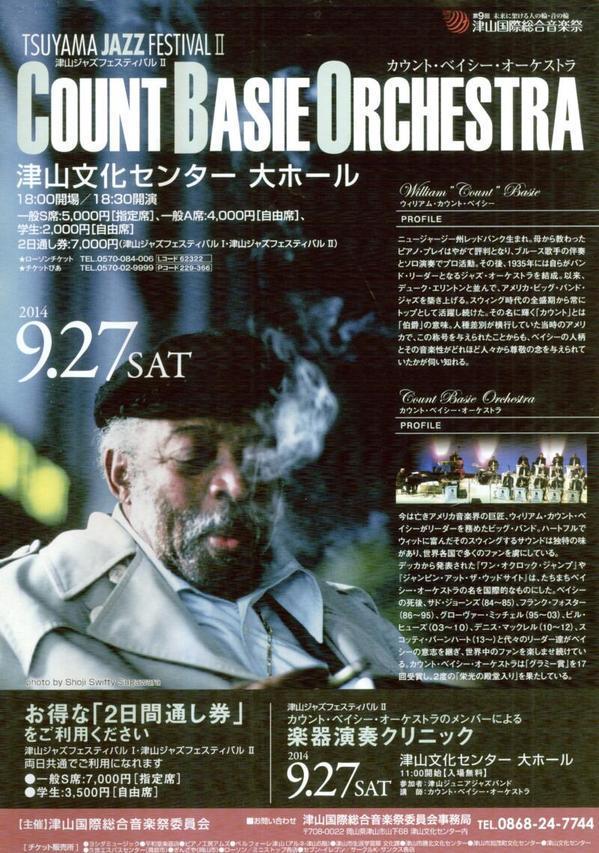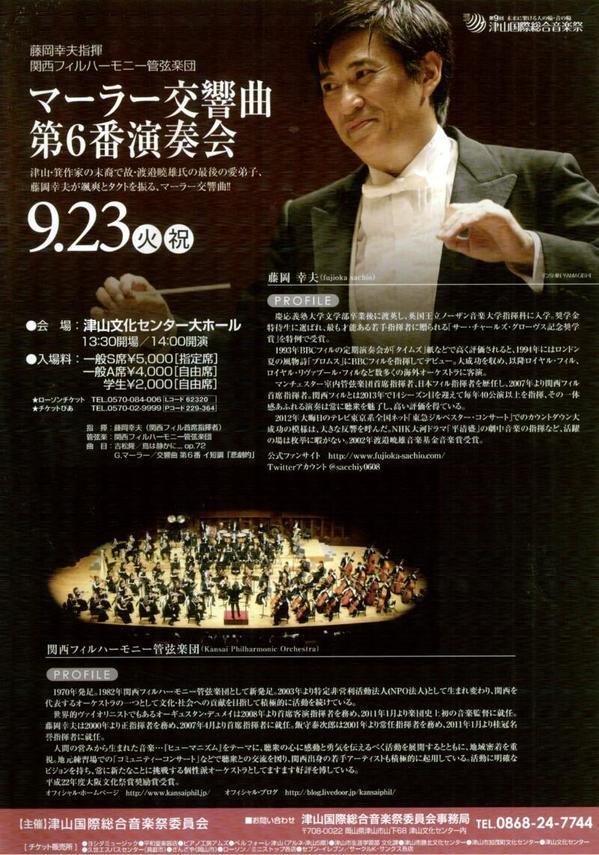出雲街道・因幡往来の分岐点 玉琳の三叉路(津山市川崎字玉琳)
ここには、信仰に関わる多くの石造物がある。
○回国供養塔《玉琳鎮座の石塔=文化11年(1814)》
回国供養塔は、通称 六部の碑と呼んでいるが、正しくは「全国六十六部廻国供養塔」のことである。世の平穏や民生の安定を願って全国六十余州の有名社寺を行脚して、法華経札を納めて回る編歴の僧侶たちを本来、六十六部と称した。しかし、江戸末期には次第に行脚が大衆化して、村々を回って戸ごとに拝み米や銭のお布施をもらって歩く、遍路姿の巡礼者たちをも総称して六部と言うようになった。彼らは、廻国道中に仲間や村人の協力を得て、往来の多い道筋あたりにこうした供養塔を建立した。
玉琳の三叉路付近は、人の出入りの盛んなまさに交通の要衝の地であり、近くに日吉神社も在ることから、絶好の位置に鎮座して祀られているといえる。(2014.6.15)