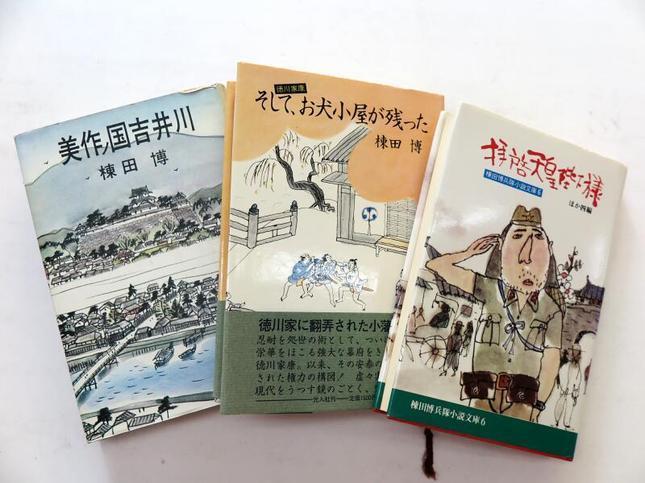「B'z 津山を盛り上げる会」で春のおもてなし。
ROUTE178 B'z津山を盛り上げる会(二番街・津山銀天街・元魚町商店街)の皆さんが、津山さくらまつりの一環として企画されておられる楽しそうなイベントを取材させていただきました。なんと、デグチビル側面には看板が設置され、また、「ROUTE178 B'z津山を盛り上げる会(イナバ化粧品店協賛)」の常夜燈が12基設置されました。会長の出口剛三さんは「昨年の津山公演も、その後の、お誕生日おめでとう会や多くのファンの人たちと触れ合えとても感動した。もっと早くにしてあげればよかった!」と反省しきり。夏には、B'z結成30周年記念を企画中だとか。とっても楽しみですね~。(昔の元魚町商店街)