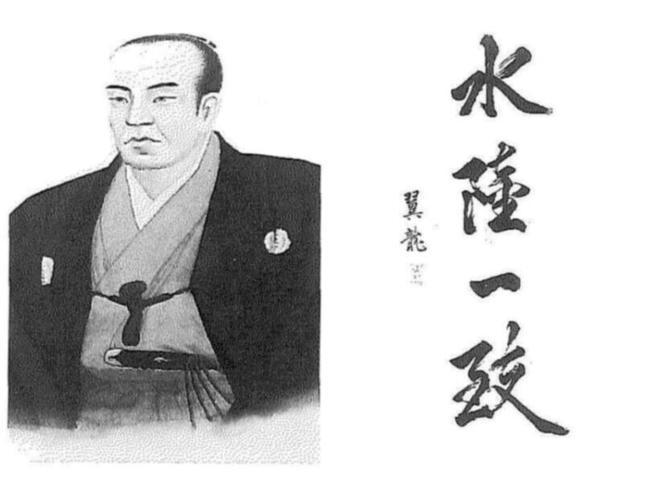「真言宗立教開宗1200年慶讃記念法会」に東寺参拝
津山市河面にある「墨池山 清瀧寺」の本山である東寺で、100年に一度の真言宗立教開宗1200年の慶讃大法会が(2023年10月8日~14日)あり、10月8日に檀家の皆さんと参拝してきました。初めて参加する大法会は、厳かであり、華やかでもありました。この法要で清瀧寺の滋澤弘典住職が、開白(かいびゃく)の座で誦経導師(じゅきょうどうし)という大役を務められました。し~んと静まり返った金堂の境内に弘典住職の良く通る声が響き渡っていました。
また、住職の次女さんが、昨年、東寺伝法学院で僧侶となるべく、一年間の修行をされたと聞きました。そして、同期に修行された尼僧さんが、東寺諸堂の案内役を担当してくださいました。尼僧さんの案内で親しみが増しました。
娘さんは、「お父さんに尊敬の念が増し、高齢者にも若い人にも子ども達にもいろいろな人に寄り添えるお坊さんになりたい。」とのことでした。僧侶としての活躍を期待しています。