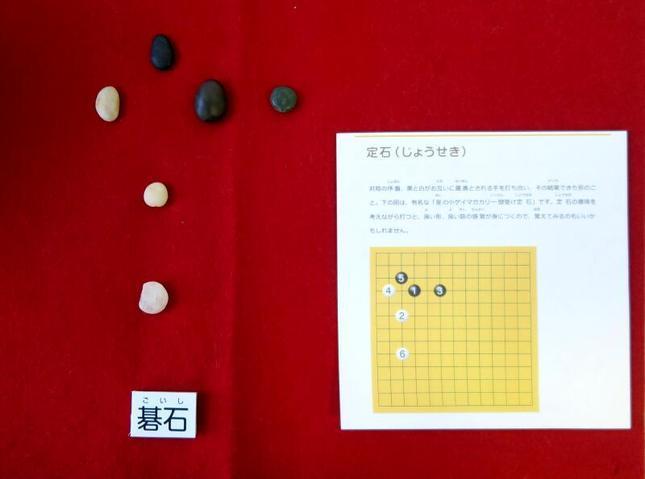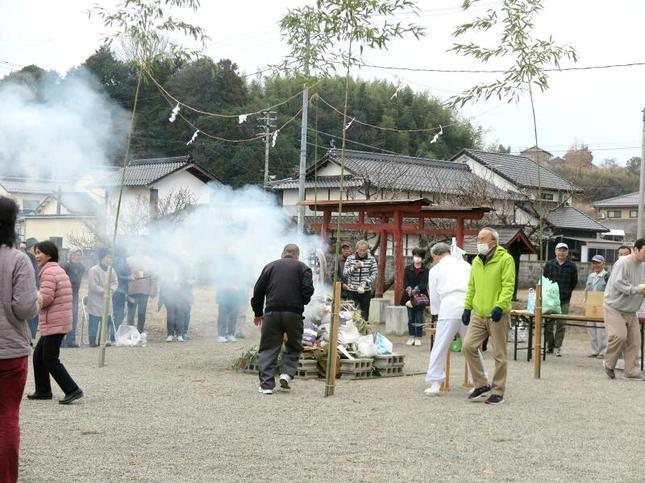津山でポケだちの輪広げようが開催されました。
2020年1月19日(日)(13:00~17:30)城西公民館に於いて「津山でポケだちの輪広げよう」が開催されました。この会はポケモンカードゲームを通じて交流をしようという趣旨だそうです。それに、参加費50円という随分リーズナブルなお値段です。
初心者がおそるおそる部屋に入ってみたら、あらっ!なんと可愛い子どもたちが真剣な眼差しでカードゲームを楽しんでいるではありませんか。ポケカは、「デッキ」という60枚のカードを使ってバトルをするゲームで、みなさんお気に入りのポケモンカードを集めてゲームをします。ポケモンカードには、可愛いキャラクターが沢山描かれていて楽しそうです。


 http://www.e-tsuyama.com/
http://www.e-tsuyama.com/