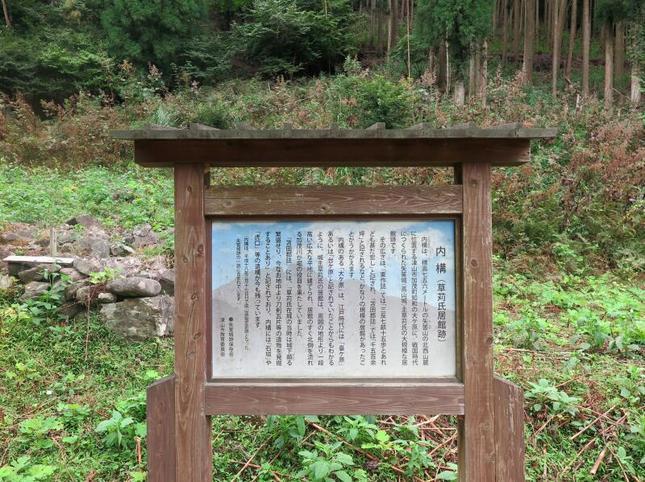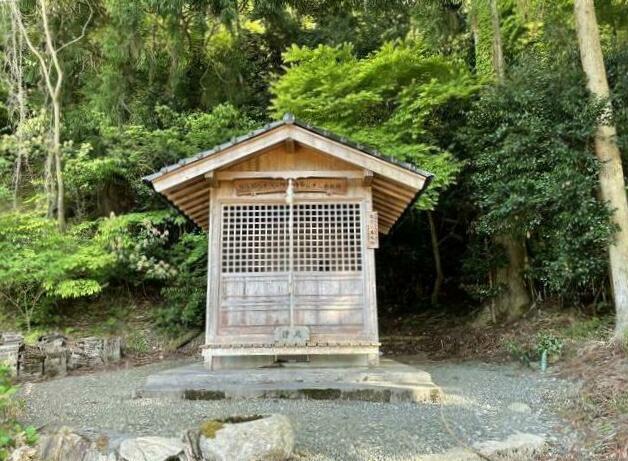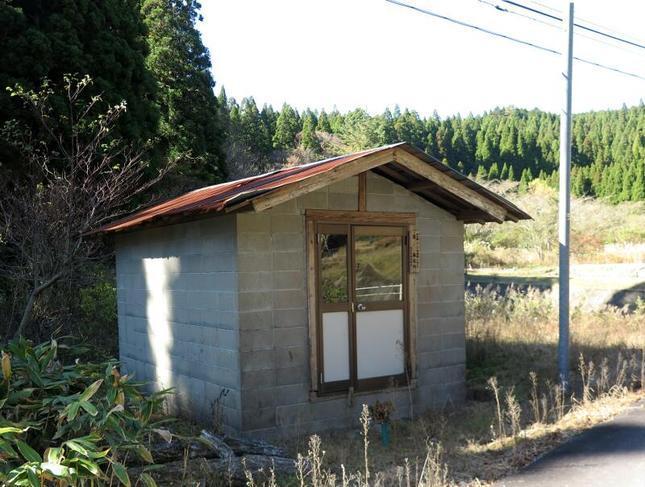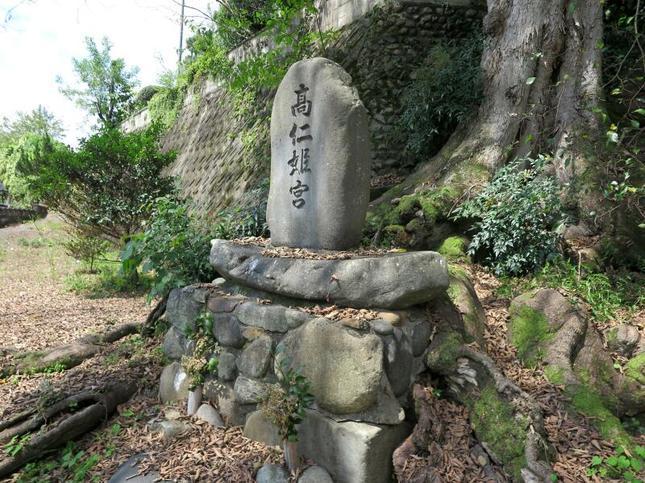県道・物見峠の改修(津山市物見)
物見峠を越えて因幡国へ通じる県道(旧因幡街道)の改修について、以前この県道は、公郷から下津川までの間を松ヶ乢(たわ)越といって、現県道より上の山腹を通じていたが、明治中期頃に現在位置の道筋に変更されている。
この詳細については不明であるが、明治19年頃に勝北郡堀坂村より物見村までの改修工事が行われたことが、豊岡貢所蔵文書によってわかる。
また、桑原地内の旧道は、旧加茂東小学校前を通り、井手の上手から井手に沿って藤の木までであったが、これは昭和3年(1928)3月の因美線津山-加茂間の開通にともなって大改修が行われ、道筋も公郷・桑原両地内をほぼ直線で貫通する現県道筋となった。
その後、この道路は、昭和37年(1962)10月の県営黒木ダムの建設にともなう資材輸送のために拡幅・整備がなされ、翌38年春、工事が完しその両目を一新した。
このような道路変更にともなって町並も変わった、すなわち、因美線の開通以前には、往来筋に民家も建ち並んで「町屋敷」とよばれ繁盛していた旧道筋は、県道路線変更によってさびれていたので、これに沿った民家も次々と新県道沿いの場所へと移動していき、現在のような町並を形成するにいたった。